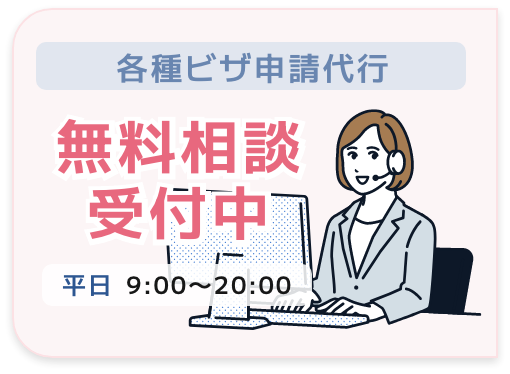医療ビザは医療従事者として働くための在留資格です。医療ビザを取得するには、必要書類を十分に準備し、正しい申請手続きをする必要があります。
この記事では、医療従事者として働くための医療ビザについて、申請する手続きの流れや条件、必要な書類などを解説します。日本の医療関係の資格を有している外国人を医療従事者として雇用したい企業の方はぜひ参考にしてください。
医療ビザの申請は豊富な実績も持つMIRAI行政書士事務所へのご相談がおすすめです。無料相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
医療ビザと医療滞在ビザの違い
医療ビザと医療滞在ビザは大きく以下の違いがあります。
- 医療ビザ:医療従事者として働くための在留資格
- 医療滞在ビザ:医療を受けることを目的とした在留資格
在留資格の内容は大きく違いますが、名称が似ているため、混同することのないように事前に確認しておきましょう。
医療ビザは医療従事者として働くための在留資格
日本の医師免許を持った外国人が、資格の範囲内で医療関係の仕事に就くために必要なのが医療ビザです。対象者は医師、歯科医師、薬剤師、看護師など多岐に渡りますが、いずれも日本の医療資格を持つ人材であることが求められます。
外国で医療に関する資格を取得していても、日本の資格を取得していなければ医療ビザの要件を満たさないので注意しましょう。また、医療ビザの在留期間は、5年、3年、1年、3か月のどれかとなっています。
医療滞在ビザは医療を受けるための在留資格
医療滞在ビザは、日本で治療や医療を受けることを目的として訪日する外国人患者が取得できる在留資格です。人間ドック、健康診断、検診、歯科、治療、療養などを受ける場合に認められます。また、医療滞在ビザの在留期間は、90日以内、6か月または1年であり、病態等を踏まえて期間が決定されます。
医療ビザの申請の流れ
医療ビザの申請をする際、正しい流れで手続きを進める必要があります。
- 申請書作成
- ビザの申請
- 審査
- ビザの交付
正しい手順、方法で申請できなかった場合、ビザ申請が不許可になる可能性もあるため、事前に必ず確認しておきましょう。
申請書作成
まずは、出入国在留管理局に提出する書類を作成します。医療ビザの申請における必要書類は以下です。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒
- 申請人の日本の資格を有することを証明する文書(医師・歯科医師の場合は免状または証明書等の写しが必要)
- 勤務する機関の概要を明示する資料
医師・歯科医師以外の医療従事者としてどのような職種が該当するかについては、「医療ビザを取得するための資格要件」にて解説しています。主に、薬剤師や看護師、歯科衛生士等が該当します。
ビザの申請
必要な書類を揃えたら、出入国在留管理局に医療ビザの申請を行います。書類内容に不備があるとビザの取得が認められない可能性があるため、医療ビザの申請前には必ず必要書類が本当に揃っているか、必要な項目はすべて満たしているかを確認しましょう。
また、本人以外でも医療ビザの申請は可能です。当該外国人を受け入れ予定の機関の職員や法定代理人等の申請取次者などが本人の代理で申請できます。
審査
出入国在留管理局に申請をした後、医療ビザ交付の審査に入ります。医療ビザの審査で特に審査されるポイントは、日本で医療従事者として就労できる資格を取得しているかどうかです。
また、招聘条件についても審査が入ります。医療ビザ交付後に勤務予定の医療機関や薬局を明示しておくことが大切です。審査期間としては、1か月〜3か月程度と考えておくと良いでしょう。
ビザの交付
医療ビザの申請に問題がなければ、数日でビザの交付が行われます。しかし、書類の不備や追加書類の提出を求められた場合、追加で時間がかかるので万全な準備をして医療ビザの申請に取り掛かりましょう。
もし、医療ビザの申請が不許可になってしまった場合は、不許可理由を直接確認しておく必要があります。不許可理由を解決させ、再申請に向けて取り掛かりましょう。
参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/medicalservices.html
医療ビザの取得条件
医療ビザにはいくつかの取得条件があります。
- 資格要件
- 准看護師特有の要件
- 招聘要件
医療ビザを申請する前に条件を満たしているか、事前に確認しておきましょう。
資格要件
医療ビザの取得で最も重要な点として、従事する医療関係の資格を有しているかどうかが挙げられます。
- 医師
- 歯科医師
- 薬剤師
- 保健師
- 助産師
- 看護師
- 准看護師
- 歯科衛生士
- 診療放射線技師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 視能訓練士
- 臨床工学技士
- 義肢装具士
上記の医療に関する日本の資格のいずれかを最低限取得している必要があります。歯科技工士、マッサージ師、鍼灸師、柔道整復師などは医療ビザの職種に該当しないため、注意しましょう。
参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/medicalservices.html
准看護師特有の要件
准看護師には特別な条件があります。外国人が准看護師として業務する場合、資格を取得してから日本に在留できるのは4年のみです。
そのため、正看護師の資格を在留中に取得したり、「技術・人文知識・国際業務」や「家族滞在」などの在留資格に変更したりするなど、在留期間の延長をしなければなりません。資格を取得してから4年が経過していると、准看護師として就労することはできないので、注意しましょう。
招聘要件
以下の職種の場合、医療ビザを取得していた場合でも、日本の薬局や医療機関に招聘されないと就労することができません。
- 薬剤師
- 歯科衛生士
- 診療放射線技師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 視能訓練士
- 臨床工学技士
- 義肢装具士
薬局や医療機関に招聘されれば、在留資格認定証明書等の申請手続きを行うことで、上記の職種で就労することが可能になります。
医療ビザ申請時の注意点
医療ビザの申請時には正しい書類作成も重要ですが、他にも注意点があります。
- 業務範囲外の就労は不可
- 受け入れ医療機関における就労環境整備が不可欠
- 日本人と同等以上の給与設定が必要
- 定期的な更新が必要
これらは就労ビザを取得する際に共通する注意点です。以下でそれぞれ解説していきます。
業務範囲外の就労は不可
医療ビザの交付は、当該外国人が医療機関等で専門業務に従事することが前提です。医療に関連する業務であっても、事務作業や介護業務の一部は医療ビザで定める業務の範囲外となる可能性があります。
定められた業務内容以外の就労が含まれていると、ビザ申請が不許可になる可能性があるため、雇用契約時に就労予定の業務について、明示しておくことが大切です。
受け入れ機関における就労環境整備が不可欠
医療ビザの審査では、受け入れ機関で適正な就労環境が整備されているかどうかも重要視されます。外国人を受け入れる体制として、日本語の研修制度などを整備していると良いでしょう。特に医療系職種では、日本語の齟齬などが発生すると患者とのトラブルが発生する可能性も考えられます。
日常的に高いレベルの日本語力を求められるため、日本語研修制度の整備は審査の際にプラスにはたらくでしょう。このように受け入れ機関の就労環境が適正かどうかを証明できなければ、在留資格が認められない可能性があります。
日本人と同等以上の給与設定が必要
当該外国人の賃金が、年齢や業務内容の似ている日本人と同等以上の水準であるかも注意が必要です。外国人であることを理由に不当に給与を低く設定していた場合、医療ビザの交付は認められません。また、夜勤や時間外労働が発生しやすい医療現場では労働時間と給与の設定が厳しくチェックされる場合があります。医療ビザの申請前に受け入れ機関の給与設定は必ず確認しておきましょう。
参考:https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin13/sisin01.html
定期的な更新が必要
医療ビザを申請する際に多くの注意点やポイントがありますが、医療ビザ取得後にも大きな注意点があります。それは、医療ビザの在留期間更新が必要だということです。医療ビザは、在留期間が満了する概ね3か月前から更新手続きが可能になります。
医療ビザの更新には主に以下の書類が必要です。
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート及び在留カード
- 住民税の課税(または非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 従事する職務の内容及び報酬を証明する在職証明書その他の所属機関の文書
在留期間の更新を行わないと、当該外国人は日本での不法滞在となり、日本国内での就労や滞在が認められなくなってしまいます。医療ビザ取得後の注意点にはなりますが、申請時から念頭に置いておきましょう。
まとめ

医療ビザは、日本で医療に従事する外国人が取得する在留資格です。本記事で解説したように、必要書類を正確に準備し、ポイントを押さえて正しく申請できれば、医療ビザの取得は可能です。
しかし、多くの書類を準備したり、煩雑な申請手続きを進めていったりするには大変な労力がかかります。そこで、医療ビザの申請では、行政書士の申請代行がおすすめです。
MIRAI行政書士事務所では、医療ビザの申請で困った方向けに申請代行を行っており、豊富な実績もあります。医療ビザについて不安を感じている方は、ぜひ一度ご相談ください。