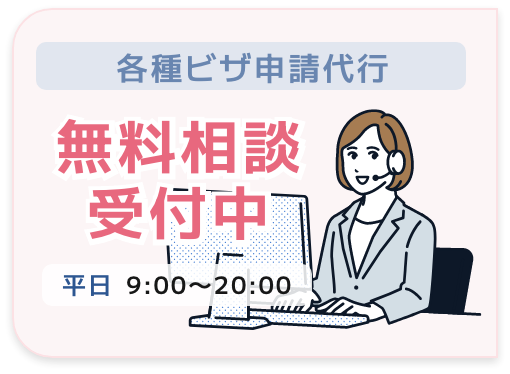慢性的な人手不足に悩む企業が注目する在留資格が「特定技能2号」です。1号と異なり在留期間に上限がなく家族帯同も可能なため、熟練人材の長期定着と技能継承が期待できます。
本記事では制度概要と取得要件、雇用コスト最適化効果、活用事例を交えながら詳しく解説し、導入時の注意点も紹介します。さらに他制度との違いを整理し、採用戦略に活かせるヒントを提供します。
特定技能2号
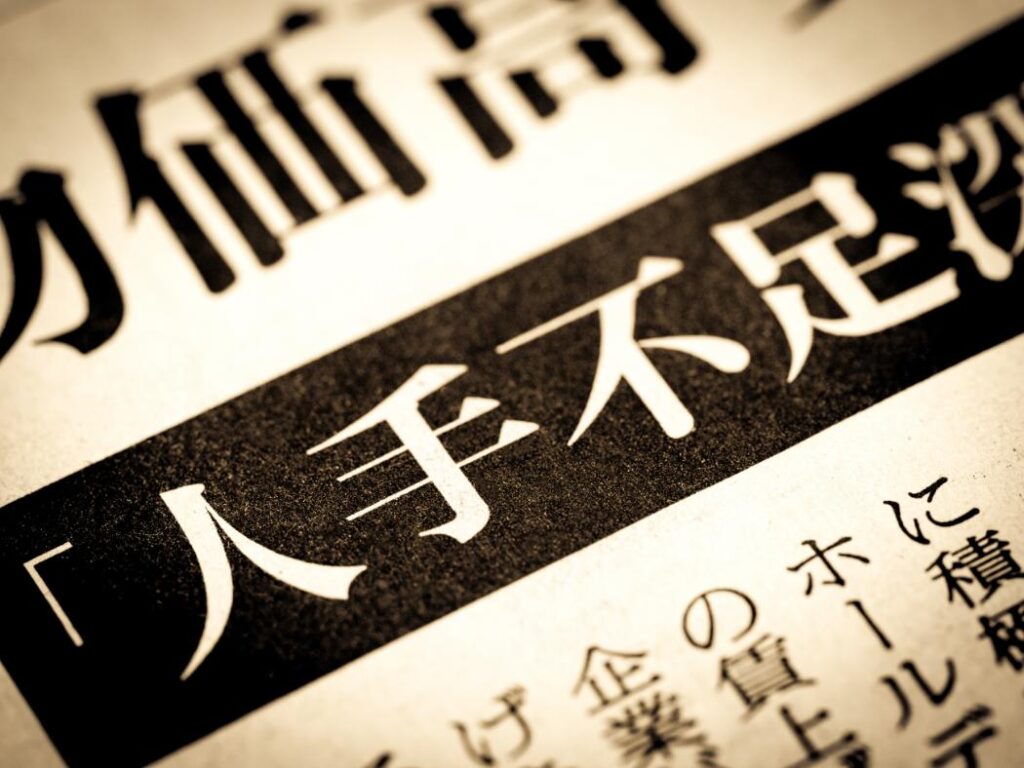
特定技能2号は、慢性的な人手不足に直面する産業で熟練人材を長期的に確保するために創設された在留資格です。最大の特長は在留期間に上限がなく、更新を重ねれば無期限就労が可能になる点です。
また、配偶者や子どもの同伴が認められているため、労働者は日本で安定した生活基盤を築きやすく、離職リスクが低減します。
さらに、受入機関に義務づけられていた生活支援が不要であるため、企業側の負担とコストを抑えつつ、技能継承と人材定着を図れます。
特定技能1号と2号の違いとは

両資格の決定的な相違点は在留期間、家族帯同、支援義務の三点です。1号は在留通算5年の上限と家族帯同の不可が設定され、受入企業には生活支援義務があります。
一方、2号は更新回数に制限がなく、配偶者・子どもの帯同が可能で、支援義務も免除されます。ただし、2号の対象は現時点で建設と造船・舶用工業の二分野に限定され、技能試験の難易度も高めに設定されています。
特定技能2号の人材を雇用するメリット
特定技能2号の人材を雇用することには、いくつかの重要なメリットがあります。これから説明するメリットを活かすことで、企業は人手不足の解消と業務の効率化を図ることができます。
更新すれば永続的に雇用し続けられる
特定技能2号の最大の特徴の一つは、在留期間に上限がないため、更新を行うことで永続的に雇用し続けることが可能な点です。建設や造船のように技能継承が品質に直結する現場では、長期在籍者が工程短縮や事故防止に貢献し、組織の安定性が高まります。
採用・再教育コストを削減できるだけでなく、長期で養ったノウハウを内部に蓄積できるので、競争優位の基盤が強化されます。
また、就労者本人も将来のキャリアパスを描きやすくなるため、モチベーションが維持され、結果として職場定着率が向上します。
専門的なスキルを持った人材を雇える
2号取得者は高度な技能試験を突破しているため、採用即日から重要工程を任せられます。たとえば建設分野では型枠施工や配管、造船では溶接や艤装など熟練度の高い作業を自立して遂行可能です。
これにより再工事や品質不良による損失を削減できるほか、若手へのOJTが効率化し、全体の技能底上げにつながります。多様なバックグラウンドを持つ人材が持ち込む新しい知見は新規事業開拓や技術革新の契機にもなり得ます。
受け入れ機関による義務的支援が必要ない
特定技能1号で義務付けられている11項目の生活支援は、2号では免除されています。企業は通訳手配や住宅確保に伴うコストを削減でき、人事担当者の負担も軽減されます。
ただし、支援が不要でも、日本語研修や社内相談窓口を設けることで定着率が高まり、パフォーマンスが向上します。義務撤廃による柔軟性を活かしつつ、企業文化に合わせた自主的サポート体制を整えることが長期雇用のカギです。
特定技能2号の特徴とは
特定技能2号は、在留期間の上限がなく、更新も可能なため、企業にとって非常に魅力的な制度です。ここではいくつかの特徴について解説します。
在留期間の上限・更新回数
特定技能2号では在留期間に上限がなく、更新回数も無制限です。初回許可後に要件を満たし続ければ、理論上永続的に就労できるため、企業は熟練人材を長期戦力として活用できます。
これにより、技能伝承やサービス品質の安定化を図りつつ、採用・育成コストを抑制できます。また、労働者も生活設計を長期視点で立てやすく、職務継続へのモチベーションが向上します。この無期限性こそが1号との差別化ポイントです。
永住申請の年数要件
特定技能2号を取得した外国人が永住権を申請する際には、一定の年数要件が設けられています。具体的には、特定技能2号の在留資格を持つ者は、日本において5年以上の在留が必要です。
この期間中には、安定した収入や納税実績が求められ、社会に貢献していることが重要視されます。特定技能2号は、長期的な雇用を前提としているため、企業にとっても熟練した人材を確保しやすく、技能の継承が進むメリットがあります。
家族帯同の可否
特定技能2号の大きな特徴の一つは、家族帯同が可能である点です。これにより、外国人労働者は日本での生活をより安定させることができ、仕事に専念しやすくなります。
家族が一緒に生活することで、精神的なサポートを受けられるため、労働者のモチベーション向上にも寄与します。
また、家族帯同が認められることで、特定技能2号の魅力が増し、優秀な人材を引き寄せる要因となるでしょう。企業にとっても、長期的に安定した雇用関係を築くための重要な要素となります。
支援義務の有無支援義務の有無
特定技能2号の制度においては、受け入れ機関に対する支援義務が存在しない点が大きな特徴です。特定技能1号では、外国人労働者に対して生活支援や日本語教育などの義務が課せられていますが、2号ではそのような義務が免除されます。
支援義務がないことで、企業は自社のニーズに応じた採用や教育プログラムを自由に設計できるため、効率的な人材活用が可能です。
また、企業側の負担が軽減されるため、特定技能2号の人材を受け入れる際のコストも抑えられるというメリットがあります。
特定技能2号に関する注意点とは

特定技能2号を導入する際にはいくつかの注意点があります。これから解説する点を考慮し、計画的な採用戦略を立てることが重要です。
特定技能2号の試験は企業が申し込む場合が多い
特定技能2号に必要な評価試験は、多くの場合で雇用予定企業が申し込み手続きを担当します。企業は自社業務に合致する技能区分の試験を選定し、応募者のスキルを的確に測定できます。
また、受験料や会場手配を企業が負担することで候補者の経済的障壁が下がり、優秀な人材を確保しやすくなります。ただし、書類準備や試験日程調整など煩雑な業務が伴うため、担当部署と現地パートナー間でタスクを明確化し、余裕あるスケジュール管理が重要です。
実務経験は、2年以上という制約がある
特定技能2号の申請には対象業種で2年以上の実務経験が必須です。この要件により企業は即戦力を確保できますが、採用段階で経験内容を詳細に確認し、証明書類を精査する必要があります。
経験豊富な人材は業務の立ち上がりが早く、指導者としても機能するため、生産性向上と技能継承を同時に進められます。
ただし、経験年数を満たしていても業務範囲が狭い場合はギャップが生じる恐れがあるため、入社後の補完教育を計画しておくと安心です。
まとめ
特定技能2号は、企業が人手不足を解消し、熟練した人材を長期的に雇用するための有力な選択肢です。制度の特徴や雇用メリットを理解することで、企業はより効果的な採用戦略を立てることができます。
特に、在留期間の上限がないことや家族帯同が可能な点は、労働者にとっても大きな魅力です。今後の人材確保に向けて、特定技能2号の活用を検討することが重要です。