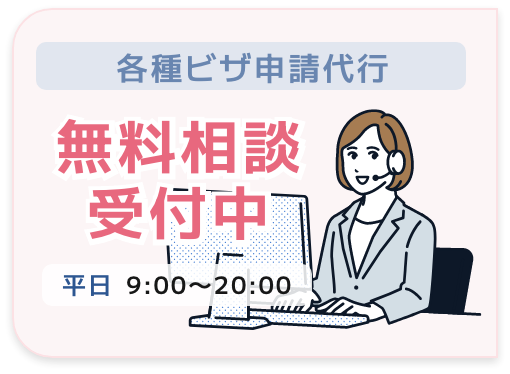急増する介護ニーズに応えるため設けられた介護ビザですが、この資格で永住権取得を目指すには在留年数、収入要件、介護福祉士資格の保持など複数の条件をクリアする必要があります。
本記事では、介護ビザとEPAや特定技能との違いを整理し、永住権への最短ルートや実務上の注意点、資格取得方法ごとの学習コストまで詳しく解説します。さらに永住後のキャリア形成や家族帯同の可否についても触れます。
介護ビザで日本に永住できるのか

介護ビザを保有していても自動的に永住できるわけではありませんが、介護ビザのまま在留期間を3年または5年単位で更新しながら10年以上日本に居住することは可能です。
そのうち就労系在留資格として5年以上勤務し、住民税・所得税・年金・健康保険料を滞納なく納付し続けるなど永住許可ガイドラインに規定された要件を満たせば永住申請は認められる可能性があります。
技能実習や特定技能1号で過ごした年数は原則カウントされないため、早期に介護ビザへ切り替えることが重要です。
また、日本語能力試験N2相当の語学力、平均年収300万円前後以上の安定収入なども審査で確認されます。介護福祉士資格を維持しながらキャリアを積み、社会統合要件を丁寧に整えることで、慢性的な人手不足が続く介護業界に貢献しつつ永住権取得を目指せます。
さらに、扶養家族の在留資格も事前に整えておくと審査が円滑になり、許可後は就労制限が消えるため多様な昇進機会が得られます。計画的な証拠資料収集と専門家の助言が成功率向上の鍵になります。
介護に関連した在留資格とは

日本における介護に関連した在留資格は、外国人が介護業界で働くための重要な枠組みです。主な資格には「介護ビザ」、EPA(特定活動ビザ)、技能実習(介護)、特定技能(介護)があります。
介護ビザ
介護ビザは、国家資格である介護福祉士登録を前提とした就労在留資格で、介護サービス全般を無期限で行える点が最大の魅力です。初回在留期間は1年・3年・5年のいずれかで付与され、更新回数に制限がないため長期雇用やキャリアアップに直結します。
申請時には、介護福祉士登録証、雇用契約書、給与が日本人同等以上であることを示す資料、施設の決算書などを提出します。
また、配偶者や未成年子は家族滞在ビザで帯同可能で、将来的な永住申請でも就労系資格として在留年数が通算されます。国家試験の直近合格率は留学生6割強、EPA候補者4割弱であり、専門学校2年以上のカリキュラム修了者は合格率が高い傾向にあります。
更新時は、処遇改善加算取得状況や人員配置基準順守も確認されるため、勤務先の運営体制を継続的にチェックすると安全です。現場経験を重ねてケアマネ資格を取得すれば管理職登用の道も開けます。
EPA(特定活動ビザ)
EPA(Economic Partnership Agreement)とは、日本と特定の国との間で締結された経済連携協定に基づく在留資格の一つです。このビザは、主に介護分野において外国人が日本で働くことを可能にするために設けられています。
介護ビザへの登竜門として注目されるEPA介護候補者向け特定活動ビザは、日本とフィリピン・インドネシア・ベトナムなどの経済連携協定締結国から人材を受け入れる制度です。
候補者は来日後に日本語研修を受け、施設で働きながら介護福祉士国家試験に挑戦し、3〜4年以内に合格すれば介護ビザへ変更できます。不合格の場合は帰国となるため、N2レベルの日本語力と試験対策が必須です。
直近の第37回試験ではEPA候補者の合格率が約38%であり、サポート体制の手厚い施設を選ぶことが合格への近道です。EPAルートは家族帯同不可ですが、介護ビザへ変更後は帯同可能となり、永住申請に向けた在留年数もカウントされます。
施設側は受入費用を負担する代わりに即戦力を確保できる利点があり、合格後は処遇改善加算の算定要件も満たしやすくなるため、定着率向上につながります。
技能実習(介護)
介護ビザを目指す初期段階として利用されることが多いのが技能実習(介護)です。在留期間は最長3年+延長2年の合計5年に限定され、家族帯同や永住権申請年数のカウントは認められていません。
ただし、3年以上の実習を修了し、介護技能評価試験と日本語能力試験N3以上に合格すれば特定技能1号へ、さらに国家試験合格後は介護ビザへ移行できます。
実習中は監理団体が労働環境をチェックしますが、未払い賃金などのトラブル例も報告されるため、受入施設の実績を見極めることが重要です。
制度は2027年に見直し予定で、職種区分や在留上限が変更される可能性があるため、長期在留希望者は実習期間中から日本語学習と国家試験対策を進め、円滑に上位資格へ乗り換える準備を整えておくと良いでしょう。現場経験の積み重ねこそ次へのステップになります。
特定技能(介護)
介護ビザへ直結しやすい中間ルートが特定技能1号(介護)です。技能試験と日本語能力試験N4以上の合格を要件に、最長5年間、日本人と同等以上の報酬で介護業務に従事できます。
在留期間中に介護福祉士国家試験に合格すれば介護ビザへ変更でき、永住権取得に必要な在留年数カウントが始まります。家族帯同は認められていないものの、入管は労働条件を定期報告でチェックしているため環境は改善傾向です。
2025年度以降、年間受入枠が約5万人まで拡大予定で、待遇競争が進んでいます。受入施設が試験対策講座や日本語学校費用補助を用意する例も多く、来日初年度から学習習慣を確立すれば合格率が高まります。
施設の教育体制と処遇改善加算の取得状況を確認し、キャリアアップしやすい職場を選ぶことが成功への近道です。
介護ビザの取得条件とは

介護ビザを取得するためには、いくつかの重要な条件を満たす必要があります。これから解説する要件をクリアすることで、介護ビザの取得が可能となります。
介護福祉士の資格を有していること
介護ビザ取得の核心要件である介護福祉士資格は、国家試験合格と登録手続きを経て初めて有効になります。受験には養成施設2年課程修了、大学介護系学科卒業、または実務経験3年以上+実務者研修修了のいずれかが必要です。外国人の場合、日本語問題が大きな壁で、直近試験では留学生合格率約63%、EPA候補者約38%にとどまります。
資格取得で処遇改善加算区分を上げられるため、施設側も賃金・役職で優遇しやすく、永住申請の安定収入要件クリアにも直結します。
2019年改正でカリキュラムに医療的ケアが組み込まれ、喀痰吸引や経管栄養を学ぶため、取得者は医療・看護連携のハブとしても重宝されます。地方の医療介護連携推進地域からの求人も増えており、資格保持者は勤務地選択の自由度が高まります。
日本の介護事業所と雇用契約を結んでいること
介護ビザ申請では、申請者が介護保険法上の指定事業所または老人福祉法に基づく施設と常勤雇用契約を締結していることが必須です。契約書には労基法所定事項を明示し、賃金が日本人同等以上である旨を示す就業規則や賃金テーブルも添付します。
事業所側が入管法違反や基準省令違反で是正命令を受けていないか、処遇改善加算を適切に配分しているかも審査対象となります。直近の決算書・納税証明書・職員配置表を提出するのが一般的です。
夜勤専従や短時間勤務へ異動しても週30時間以上を維持していれば常勤扱いとなりビザ要件を満たします。パート契約へ変更する場合は条件を満たさなくなる可能性があるため、異動時には在留資格条件との整合性を確認しましょう。
施設が労基署や介護保険指導監査で違反を指摘された場合、更新時に不利益が及ぶ例もあるため職場選びに留意が必要です。
業務内容が介護に関連していること
介護ビザを取得するためには、業務内容が介護に関連していることが重要な条件の一つです。具体的には、介護ビザを持つ外国人が従事する業務は、高齢者や障害者の生活支援、身体介護、医療的ケアなど、介護サービス全般にわたります。
これにより、介護ビザ保持者は日本の介護現場で必要とされる専門的なスキルを活かし、実際に介護業務に従事することが求められます。
また、業務内容が介護に関連していることは、雇用契約の内容にも反映される必要があります。具体的には、契約書に明記された業務内容が介護に関するものであることが求められ、これが確認されることで在留資格の更新や永住権の申請がスムーズに進むことになります。
したがって、介護ビザを取得したいと考える方は、雇用先の介護事業所が提供するサービス内容をしっかりと理解し、自身の業務がその中に含まれていることを確認することが重要です。
日本人と同等以上の報酬を受けること
介護ビザを取得するための重要な条件の一つが、日本人と同等以上の報酬を受けることです。この要件は、外国人労働者が日本の労働市場において公平に扱われることを目的としています。
具体的には、介護職に従事する外国人が、日本人の介護職員と同じかそれ以上の給与を得ることが求められます。この条件を満たすためには、雇用契約を結ぶ際に、給与水準をしっかりと確認することが必要です。
介護業界は地域や施設によって給与に差があるため、事前に情報収集を行い、自身のスキルや経験に見合った報酬を得られる職場を選ぶことが重要です。また、介護福祉士の資格を持っている場合、より高い報酬を得るチャンスが広がります。
さらに、報酬が日本人と同等以上であることは、永住権取得の際にも大きな影響を与える要素となります。
安定した収入は、生活基盤を築く上で欠かせない要素であり、将来的なキャリア形成にも寄与します。したがって、介護ビザを取得する際には、報酬面についても十分に考慮することが求められます。
介護ビザの取得に必要な介護福祉士の資格を取る方法とは

介護ビザを取得するためには、介護福祉士の資格が必須です。この資格を取得する方法はいくつかあります。ここではその方法について、一つ一つ解説していきます。
専門学校で介護を学ぶ
介護福祉士の資格を取得するための一つの方法として、専門学校での学びがあります。専門学校では、介護に関する基礎知識や実践的な技術を体系的に学ぶことができ、卒業後には介護福祉士の国家試験を受験する資格が得られます。
カリキュラムには、介護の理論だけでなく、実習も含まれており、現場での経験を積むことができるため、即戦力としてのスキルを身につけることが可能です。
また、専門学校では、介護業界の最新のトレンドや法律についても学ぶことができ、卒業生は多くの介護事業所から求められる人材となります。
さらに、学校によっては就職支援が充実しているため、卒業後のキャリア形成にも大いに役立つでしょう。介護ビザを取得し、日本での永住を目指すためには、専門学校での学びが重要なステップとなります。
福祉系のコースがある高校を卒業する
介護福祉士の資格を取得するための一つの方法として、福祉系のコースが設置されている高校を卒業することが挙げられます。これらの高校では、介護に関する基礎知識や実技を学ぶことができ、卒業後には介護福祉士の資格試験を受けるための受験資格が得られます。
福祉系のコースでは、介護の理論だけでなく、実際の介護現場での実習も行われるため、実践的なスキルを身につけることができます。
また、福祉系の高校を卒業することで、介護業界に対する理解が深まり、将来的なキャリア形成にも役立つでしょう。
さらに、学校での学びを通じて、同じ志を持つ仲間と出会うことができるのも大きな魅力です。介護ビザを取得し、日本での永住を目指すためには、こうした教育機関での学びが重要なステップとなります。
介護の現場で3年以上働く
介護ビザを取得するための条件の一つに、介護の現場で3年以上働くことがあります。この要件は、実務経験を通じて介護技術や知識を深めることを目的としています。
具体的には、介護施設や在宅介護サービスなど、さまざまな現場での経験が求められます。実際の業務を通じて、利用者とのコミュニケーション能力や、介護に必要な専門的なスキルを身につけることが重要です。
また、3年以上の勤務を通じて、介護業界の実情や日本の文化に対する理解も深まります。これにより、介護福祉士としての資質を高めるだけでなく、将来的なキャリア形成にも大きく寄与します。
さらに、雇用主との信頼関係を築くことも、永住権取得に向けた大きなステップとなります。したがって、介護の現場での経験は、単なる条件を満たすためだけでなく、自己成長やキャリアアップのためにも非常に重要な要素と言えるでしょう。
EPA制度を利用する
EPA(経済連携協定)制度は、日本と特定の国との間で締結された協定に基づき、介護分野での人材受け入れを促進するための仕組みです。この制度を利用することで、外国人が日本で介護福祉士として働くための道が開かれます。
具体的には、EPAに基づく介護ビザを取得するためには、まず日本語能力試験や介護福祉士国家試験に合格する必要があります。
EPA制度の大きな特徴は、受け入れ国の人材が日本での実務経験を積むことができる点です。これにより、介護福祉士としての資格を取得するための実務経験を日本で得ることが可能となります。
また、EPA制度を利用することで、介護業界での就業がスムーズに進むため、永住権取得への道も開かれやすくなります。
この制度を活用することで、介護ビザを取得し、将来的に日本での永住を目指すことができるため、介護分野でのキャリアを考える方にとって非常に有益な選択肢となります。
まとめ
介護ビザを通じて日本に永住することは可能ですが、その道のりは決して簡単ではありません。
介護福祉士の資格を取得し、日本の介護事業所と雇用契約を結ぶことが求められ、さらに日本人と同等以上の報酬を得る必要があります。これらの条件を満たすことで、介護ビザから永住権への道が開かれます。
また、介護ビザは他の在留資格と異なり、特定の業務内容に従事することが求められるため、実務経験や専門知識が重要です。
今後のキャリア形成や家族の帯同についても考慮しながら、計画的にステップを踏んでいくことが大切です。介護業界のニーズが高まる中で、適切な準備を行い、充実した日本での生活を実現しましょう。