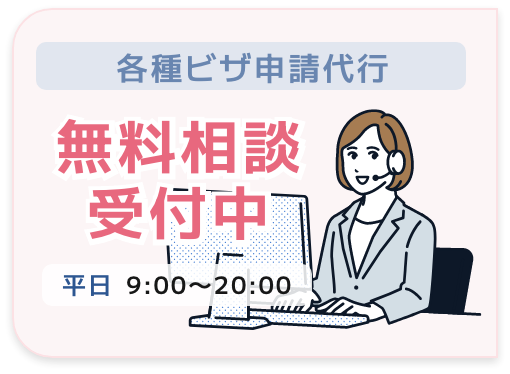「外国人を採用したいけれど、在留資格の手続きやスケジュール管理はどうすればよいのだろう。」
「どのような書類が必要なんだろう。」
外国人採用を進めるうえで、在留資格の取得や変更には細かなルールや期限があり、想像以上に手間や時間がかかることも少なくありません。
この記事では、外国人採用を検討している企業担当者や人事の方に向けて、
- 在留資格の基本的な種類と特徴
- 採用から入社までのスケジュール管理のポイント
- 注意すべき手続き上の落とし穴
上記の内容について、解説していきます。ぜひ参考にしてください。
外国人採用における基本的な手続き
外国人採用を進める際には、まず基本的な手続きの全体像や流れを把握しておくことが重要です。採用活動をスムーズに進めるためには、在留資格の確認や申請手続き、入社までのスケジュール管理が欠かせません。これらの手順を理解していないと、採用後に思わぬトラブルや法的リスクに直面することもあるため、事前準備が求められます。
なぜなら、外国人を雇用する場合、日本人採用とは異なる法律や行政手続きが必要となるからです。例えば、在留資格の種類によって従事できる業務内容が異なり、適切な資格を持たないまま雇用すると不法就労とみなされるリスクもあります。採用担当者がこうした基礎知識を持つことで、安心して採用活動を進められるでしょう。
採用計画の立案から求人・選考、在留資格の確認や申請、そして入社手続きまで、その流れについて以下で解説していきます。
外国人採用の手続き概要
外国人採用の手続きは、まず「どの在留資格が必要か」を明確にすることが最初の一歩です。採用予定の外国人が日本で働くには、在留資格が適切でなければなりません。たとえば、単純労働は認められていないため、職種や仕事内容によって申請できる在留資格が限られます。
次に、雇用契約書の作成や労働条件の明示を行い、採用者と雇用主双方の同意を得る必要があります。その後、必要書類を揃えて入国管理局への申請を進めます。手続きの進行には時間がかかるため、余裕を持ったスケジュール管理が大切です。
外国人新卒採用時の注意点
新卒の外国人を採用したいと考える際には、在留資格の取得やスケジュール管理に特に注意が必要です。まずは採用活動を始める前に「どの在留資格が取得可能か」「いつまでに申請すればよいか」を明確にし、計画的に進めることが重要です。
新卒の場合、多くは「技術・人文知識・国際業務」や「特定活動(告示46号)」の在留資格が該当しますが、卒業見込み証明書や成績証明書など、卒業予定者ならではの書類が必要となります。そして、申請から許可まで1~3か月かかることが多いため、採用内定後すぐに書類準備と申請を進めましょう。早めの準備とスケジュール管理が新卒外国人採用成功には特に必要となります。
外国人採用に必要な在留資格の種類
技術・人文知識・国際業務の取得方法
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するには、まず採用予定の外国人が大学や専門学校を卒業していること、またはそれと同等の学歴や実務経験が必要です。学歴や職務内容が在留資格の要件に合致していれば、申請手続きは比較的スムーズに進むでしょう。
なぜなら、この資格は主に事務職や技術職、翻訳・通訳などの業務に対応しており、採用する企業側も職務内容が明確であれば審査が通りやすいからです。特に仕事内容が日本人でも従事するような専門的分野であれば、審査において大きな問題にはならないと思われます。
高度専門職の在留資格取得の流れ
高度専門職の在留資格取得には、通常の在留資格よりも厳格な審査と明確な要件が求められます。まず結論として、高度専門職の在留資格を取得するには、学歴や職歴、年収などを点数化した「ポイント制」で一定基準を満たすことが絶対条件です。
この制度は、専門性や高度な知識を持つ外国人を積極的に受け入れるために設けられており、例えば大学卒業以上の学歴や、実務経験、年収などが審査対象となります。法務省の公式サイトでポイント計算表が公開されているため、事前に自己診断が可能です。 参照:「在留資格「高度専門職」(高度人材ポイント制)」出入国在留管理庁
申請には、履歴書や雇用契約書、学位証明書、年収証明書など多くの書類が必要となります。
特定活動(告示46号)の取得条件
特定活動(告示46号)の取得条件は、主に日本の大学や大学院を卒業した外国人が対象となります。卒業後に専門分野を活かした業務に従事する場合、この在留資格が認められる可能性が高いです。背景として、従来の在留資格ではカバーできない業務内容や柔軟な働き方を支援するために設けられました。申請時には卒業証明書や雇用契約書、業務内容の詳細説明書などが必要です。
特定技能の在留資格取得について
特定技能の在留資格取得は、即戦力となる外国人を雇用したい企業にとって重要な選択肢です。特定技能は、介護や外食、建設など14分野で人材不足を補うために設けられた在留資格で、一定の技能試験や日本語試験に合格した外国人が対象となります。
特定技能1号は最長5年で、家族帯同は原則認められていません。申請には雇用契約書や技能試験合格証明書などが必要になり、書類不備や不明点があると審査が長引く可能性もあります。
在留資格申請に必要な書類と手続き
必要書類の一覧
外国人採用に必要な在留資格申請では、求められる書類を正しく準備することが最初の重要なステップです。主な必要書類としては、以下のものがあげられます。
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・パスポートの写し
・履歴書
・雇用契約書
・企業の登記事項証明書
・決算書や会社案内、仕事内容を説明する書類など
上記のような書類のほか、在留資格の種類や申請者の状況によって追加書類が必要になる場合もあります。例えば、技術・人文知識・国際業務の場合は、卒業証明書や成績証明書、職務経歴書も求められることが一般的です。書類の不備や不足があると、審査が遅れたり不許可になるリスクが高まります。したがって、最新の法務省の公式情報を必ず確認し、漏れなく準備することが重要です。
申請手続きの流れ
在留資格申請の手続きは、まず必要書類を揃え、管轄の出入国在留管理局へ提出することから始まります。申請書や雇用契約書、会社案内など、求められる書類が不足していると審査が遅れるため、事前の準備が重要です。書類提出後、出入国在留管理局から追加資料の提出を求められる場合もあります。
審査期間は通常1~3か月程度ですが、繁忙期や書類不備があるとさらに時間がかかることも珍しくありません。許可が下りたら、在留カードの受け取りや住民登録など、入社前に必要な手続きを早めに進めることが大切です。
外国人採用スケジュールの立て方
外国人採用を成功させるためには、計画的なスケジュール管理が不可欠です。特に在留資格の申請や取得には一定の期間が必要となるため、採用から入社までの流れを事前に把握し、無理のないスケジュールを組むようにしましょう。在留資格申請のタイミングを誤ると、入社日に間に合わないといったリスクも生じる可能性があります。
求人開始から内定、在留資格申請、審査期間、入社準備まで、各段階で必要な期間を逆算し、余裕を持った計画を立てる必要があります。
採用から入社までのスケジュール
採用活動を始める際は、入社希望日の最低でも3~4か月前から準備を始めることが重要です。なぜなら、外国人を雇用する場合、内定後に在留資格申請書類の準備や本人とのやりとり、さらに入国管理局での審査期間(通常1~3か月程度)が必要になるためです。
事前に綿密なスケジュールを立て、内定通知、在留資格申請、審査結果の受領、ビザ発給、来日・入社という流れを明確にし、各ステップごとに余裕を持った日程管理が求められます。
在留資格申請で注意すべきポイント
在留資格申請で注意すべきポイントは、採用する外国人の仕事内容と在留資格が適切に一致しているか、そして書類の内容や申請手続きに不備がないかを丁寧に確認することです。こうした点を見落とすと、在留資格が下りずに採用計画が大幅に遅れる、あるいは不許可となるリスクが高まります。特に日本の入管は、職務内容の専門性や雇用契約の内容、企業側の受け入れ体制を厳しく審査します。例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格では、実際の業務が専門性に欠けていたり、雇用契約の内容が曖昧な場合、申請が却下されるケースも少なくありません。
仕事内容と在留資格の一致確認
仕事内容と在留資格が一致していない場合、在留資格の申請が許可されないだけでなく、後に不法就労とみなされるリスクがあります。在留資格は「どのような仕事をするか」によって細かく種類が分かれており、それぞれの資格で働ける職種が明確に定められているためです。例えば、「技術・人文知識・国際業務」は主に事務職や技術職、翻訳などが対象で、単純作業や工場ライン作業は認められていません。
職務内容を具体的に整理し、募集要項や雇用契約書の内容が在留資格の基準に適合しているか必ず確認することが重要です。この確認を怠ると、せっかく採用した外国人が働けなくなる事態も起こり得ます。
職務内容と専門性の整合性
職務内容と専門性の整合性が取れていない場合、在留資格の申請が不許可となることが多いです。なぜなら、外国人が働くための在留資格は、その人が行う仕事と学歴や職歴などの専門性が一致していることが前提だからです。経済学部卒の方を通訳業務で採用する場合、業務内容が語学力や国際的な知識を活かせるものでなければ、審査で疑問を持たれることがあります。
解決策としては、職務内容と応募者の専門性がしっかり結びついていることを、職務経歴書や内定通知書で具体的に説明することが重要です。
企業側の問題点とその対策
企業が外国人を採用する際の問題点として、採用後のフォロー体制の不足もあげられます。これらの問題が起きる背景には、日本の在留資格制度の複雑さや、外国人労働者の就労範囲に対する理解不足が挙げられます。入社後も日本語や生活面のサポート体制を整えることで、早期離職を防ぐことができます。企業側は事前準備と継続的な支援を徹底することが、外国人採用を成功させる鍵となります。
外国人本人に関する注意点
さらに外国人本人に関する注意点としてあげられるのが、在留資格の種類や有効期限、資格外活動の有無を本人が正確に把握しているかを確認することです。入社予定の外国人が自分の在留資格でどんな仕事ができるのかを理解していない場合、知らず知らずのうちに資格外活動となり、不法就労に該当するおそれがあります。
入管法違反は本人だけでなく企業にも大きなリスクをもたらします。採用前には必ず在留カードの内容を細かく確認し、必要に応じて本人と一緒に入国管理局へ相談することが大切し、その後、在留資格更新の時期や必要書類を本人任せにせず、企業側でもスケジュール管理を徹底しましょう。
外国人雇用に関する法的リスクと対策
不法就労助長罪の概要と対策
不法就労助長罪とは、在留資格がない外国人や、許可された活動内容と異なる仕事をさせることによって、不法就労を手助けした場合に問われる犯罪です。企業側が意図していなくても、知らずに外国人を不法に働かせてしまうと、経営者や担当者も刑事責任を問われる可能性があります。
対策としては、その在留資格で従事できる業務内容を必ず調べ、記録を残しておくことが重要です。また、定期的に在留期間の更新状況もチェックし、不明点があれば行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
所属機関に関する届出の重要性
所属機関に関する届出は、外国人採用後に必ず行うべき重要な手続きです。なぜなら、在留資格を持つ外国人が企業に所属した場合、入国管理局へ「所属機関に関する届出」を提出しないと、法令違反となり、最悪の場合は罰則を受けることもあるからです。この届出は、採用した外国人が実際にどの企業で働いているかを国が把握するために必要で、在留資格の更新や変更時にも影響します。届出には、会社名や所在地、外国人本人の情報などを記載し、オンラインまたは郵送で手続きできます。手続きを怠ると、企業側の信用低下や、採用した外国人の在留資格更新に支障が出る場合もあります。所属機関に関する届出は、外国人採用後の最優先事項として確実に実施しましょう。
外国人採用や在留資格に関するよくある質問
外国人採用の際の在留資格の選び方
外国人採用の際に在留資格を選ぶ際は、仕事内容と応募者の経歴が合致するかを最優先で確認することが重要です。まずは採用予定の職種と応募者の学歴・職歴・日本語力を照らし合わせ、法務省のガイドラインを参考にすることが最善です。間違った資格で申請すると不許可となるリスクも高まるため、慎重な判断が求められます。
在留資格申請の審査期間はどのくらい?
在留資格申請の審査期間は、通常1か月から3か月程度かかることが多いですが、申請内容や時期、申請先の入管局の混雑状況によって大きく異なります。たとえば、4月の新卒入社が多い時期や、年末年始などは審査期間が長引く傾向にあります。また、提出書類の不備や追加資料の要請が発生する場合には、審査期間が長期になることが多いです。
特に初めて外国人を採用する場合は、書類作成や準備に時間がかかりやすく、余裕を持ったスケジュール管理が重要となります。
外国人採用の際の手続きの流れ
外国人採用の際の手続きの流れは、「採用決定」から「入社」まで複数の段階が見込まれます。まず、採用する外国人がどの在留資格に該当するかを確認し、必要な書類を準備します。次に、在留資格の申請を出入国在留管理局へ提出し、審査結果を待ちます。審査が通れば、在留カードを受け取り、雇用契約を結びます。その後、社会保険や税務の手続き、住民登録など必要な手続きを完了させてから、入社となります。
まとめ:外国人採用の在留資格とスケジュールの要点
今回は、外国人の採用を検討している企業担当者の方に向けて、
- 在留資格の種類や取得手続きの流れ
- 採用から入社までのスケジュール管理のポイント
- 手続き時に注意すべき点やトラブル回避策
上記について、解説してきました。 参考:「日本の就労ビザの取得は難しい?条件や取得手順を解説」