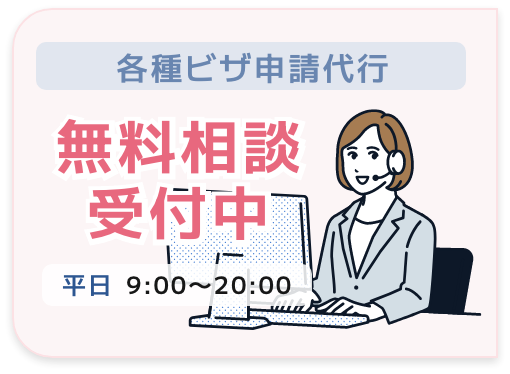在留資格「技能実習3号」は、技能実習制度のなかでもより高度な技能の習得を目指す制度です。在留資格「技能実習3号」への移行には、試験の合格だけでなく一時帰国が必須条件となります。
今回は、在留資格「技能実習3号」について解説します。在留資格「技能実習3号」の外国人労働者を雇用する際のポイントや移行制度に関する情報を知りたい方は、参考にしてください。
また、在留資格保有者の採用には、MIRAI行政書士事務所の申請代行サービスをご活用ください。書類作成から窓口申請、受け取りなどさまざまな業務を代行し、サポートいたします。
在留資格「技能実習3号」はより熟達した技能を目指す資格

在留資格「技能実習3号」は、在留資格「技能実習1号」や「技能実習2号」よりも専門的で高度な技術が習得できる制度です。
技能実習制度は、開発途上国の外国人が日本の企業で実践的な技術を学び、開発途上国の産業発展に貢献することを目的としています。在留資格「技能実習2号」で培った技術を土台に、より専門性の高いスキルを身に付けるのが狙いです。
在留資格「技能実習3号」の実習期間は4年目から5年目にあたり、特定の要件を満たせば移行が可能です。
技能実習3号の主な特徴
在留資格「技能実習3号」の主な特徴は、以下の表のとおりです。
| 在留期間 | 2年以内 |
| 対応職種 | 83職種159作業 |
| 受け入れ人数 | 上限あり |
| 転職 | 不可 |
在留資格「技能実習3号」の在留期間は、2年を超えない範囲と定められています。在留資格「技能実習1号」からカウントした場合の在留期間は、最長5年以内です。
在留資格「技能実習3号」で実習可能な範囲は、91職種168作業のうちカーペット製造や木材加工などの業務を除く、82職種148作業です(令和7年3月7日時点)。在留資格「技能実習2号」の91職種168作業に比べると、幅が狭まるといえるでしょう。
また、在留資格「技能実習3号」の受け入れは、雇用企業の常勤職員総数に応じて上限が定められています。さらに介護や建設分野では、別途人数枠が決められているのが特徴です。
在留資格「技能実習1号」や「技能実習2号」と同じく、在留資格「技能実習3号」においても転職は認められないため注意しましょう。
受け入れ方式の違いによって2つに区分される
在留資格「技能実習3号」は、受け入れ方法の違いで「イ」と「ロ」の2つの区分に分かれます。
企業単独型で外国人を受け入れた場合の区分は、在留資格「技能実習3号イ」となります。また、監理団体型で受け入れた際は、在留資格「技能実習第3号ロ」です。
在留期間は、号数が同じであれば違いはありません。そのため、在留資格「技能実習3号イ」と在留資格「技能実習3号ロ」の在留期間は、どちらも2年を超えない範囲です。
在留資格「技能実習3号イ」では受入企業の体制に応じて比較的柔軟に受入人数を決めることができますが、その分しっかりした管理能力が求められます。在留資格「技能実習第3号ロ」では受入人数に明確な上限がありますが、管理団体のサポートを受けられるので企業の負担は少なくなります。
在留資格「技能実習3号」への移行要件

在留資格「技能実習3号」への移行要件は、以下のとおりです。
- 試験に合格する
- 一時帰国をする
試験に合格する
在留資格「技能実習2号」から在留資格「技能実習3号」へ移行するには、以下のいずれかの試験に合格しなければなりません。
- 技能検定3級
- 技能実習評価試験に相当する実技試験
技能検定3級は、都道府県職業能力開発協会などが実施する国家検定です。
試験は日本語で実施されますが、外国人受験者への配慮としてふりがな付きの問題が用意されます。任意で学科試験が受けられます。
在留資格「技能実習3号」へスムーズに移行するためには、在留資格「技能実習2号」修了の2か月から3か月前までに上記の試験を受けるのが望ましいです。
一時帰国をする
在留資格「技能実習3号」では、移行前に母国へ一時帰国をしなくてはいけません。
在留資格「技能実習3号」の採用を検討している方のなかには「なぜ一時帰国をさせないといけないの?」と考える方も多いのではないでしょうか。
在留資格「技能実習」は母国の発展のために日本へ在留し、特定の技術や知識を身に付けることが目的です。そのため一時的な帰国により、習得内容の共有や母国の送出機関への報告による技能実習中の状況把握など、技能実習制度の目的を果たすことができます。
在留資格「技能実習3号」への移行を考えている場合は、以下のいずれかの条件を選択します(技能実習法第10条第2項第3号)。
- 在留資格「技能実習2号」の修了後、1か月以上帰国する
- 在留資格「技能実習3号」の開始後、1年以内に1か月以上1年未満の期間で帰国する
一時帰国にかかる費用は、企業単独型では実習実施者が負担します。団体監理型で採用した際の費用負担は、監理団体です。
なお、一時帰国期間は在留資格「技能実習3号」の実習期間には含まれません。
また、一時帰国の期間が45日を超える場合は、在留資格変更手続きに影響が出る可能性があります。そのため、新規入国手続きを検討するのがおすすめです。
帰国後は、速やかに地方出入国在留管理局で在留資格変更の申請をしましょう。
在留資格「技能実習3号」の外国人労働者を雇用する際のポイント

在留資格「技能実習3号」をもつ外国人労働者を雇用する際は、雇用企業側にも満たすべき条件があります。雇用前のポイント把握は、スムーズな申請につながるでしょう。
在留資格「技能実習3号」の外国人労働者を雇用する際のポイントは、以下のとおりです。
- 要件を満たし採用側が「優良」と認められる必要がある
- 雇用には申請手続きが必要
要件を満たし採用側が「優良」と認められる必要がある
在留資格「技能実習3号」を受け入れるには、雇用企業と監理団体の双方が「優良」と評価されなくてはいけません。
在留資格「技能実習3号」の場合、技能実習計画において「優良要件への適合」が認定基準の1つです。(技能実習法第9条第10号)認定を受けるには、技能実習計画の申請時に外国人技能実習機構(OTIT)へ「優良要件適合申告書」を提出します。
優良要件適合申告書は150点満点で評価され、うち6割の90点以上で優良認定とみなされます。主な審査項目は、以下の表のとおりです。
| 主な内容 | 配点 | |
| 技能等の修得等にかかる実績 | 過去3回の技能実習事業年度の基礎級や3級、2級程度の 技能検定の合格率 など | 70点 |
| 技能実習を行わせる体制 | 直近過去3年以内の技能実習指導員や生活指導員の講習受講歴 | 10点 |
| 技能実習生の待遇 | 技能実習生の住環境の向上への取り組み など | 10点 |
| 法令違反・問題の発生状況 | 直近過去3年以内の改善命令の実績や失踪の割合 など | 5点 ※違反は大幅減点 |
| 相談・支援体制 | 母国語で相談可能な相談員の確保 など | 45点 |
| 地域社会との共生 | 地域社会との交流をする機会 など | 10点 |
また、監理団体にも異なる許可基準が設けられており「優良要件への適合」が必須要件となります(技能実習法第25条第1項第7号)。企業と監理団体の両方が条件を満たして初めて、在留資格「技能実習3号」の受け入れが可能です。
雇用には申請手続きが必要
優良な雇用企業と認定され、在留資格「技能実習3号」の技能実習計画の申請が完了しても、在留資格「技能実習3号」の実習がすぐに始められるわけではありません。在留資格「技能実習3号」の実習開始には、在留資格「技能実習2号」からの在留資格変更の申請が必要です。
在留資格の変更申請は、管轄の地方出入国在留管理局で手続きを進められます。在留資格「技能実習3号」への変更に必要な申請書類は、以下のとおりです。
- 在留資格変更許可申請書1通
- 写真(申請書に貼付)
- 技能実習計画認定通知書
- 認定の申請書の写し1通
申請時には、パスポートと在留カードの提示が求められます。
MIRAI行政書士事務所では、在留資格の変更申請手続きの代行を承っています。申請業務の負担軽減に、ぜひ行政書士の申請代行サービスをご活用ください。
在留資格「技能実習3号」は在留資格「特定技能1号」への移行もできる

在留資格「技能実習3号」は、在留資格「特定技能1号」への申請変更が可能です。
在留資格「特定技能1号」では、転職が認められています。また、在留資格「技能実習3号」に比べて従事可能な業務範囲が広いなど、外国人の自由度が高くなるのが魅力の1つです。
ここでは、外国人労働者と雇用企業それぞれが満たすべき要件を解説します。在留資格「技能実習」と「特定技能」の違いについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
特定技能ビザと技能実習ビザの5つの違いを徹底比較!雇用時のポイントとは
外国人労働者が満たすべき要件
在留資格「技能実習3号」を修了した外国人は、一定の条件を満たせば在留資格「特定技能1号」へ移行できます。
在留資格「特定技能1号」への移行には、在留資格「技能実習2号」を2年10か月以上修了していることが必須条件です。加えて、以下のどちらかの条件を満たす必要があります。
- 技能検定3級か技能検定3級に相当する技能実習評価試験の合格
- 技能実習生に関する評価調書の提出
在留資格「技能実習2号」を良好に修了している場合は、日本語能力試験が免除されます。在留資格「技能実習3号」と在留資格「特定技能1号」の職種に関連性がある場合は、技能試験も免除対象です。
なお、在留資格「技能実習3号」の活動中における在留資格「特定技能1号」への移行申請は制度上認められていないため注意しましょう。
ただし、実習中断の手続きを正しくすれば、在留資格の変更は可能です。
雇用企業が満たすべき要件
在留資格「技能実習3号」の外国人を在留資格「特定技能1号」として採用する際は、以下の手順で進めます。
- 雇用契約の締結
- 在留資格「特定技能1号」外国人支援計画の策定
- 在留資格変更許可の申請
- 在留資格変更許可
- 就労開始
試験に合格または在留資格「技能実習2号」を良好に修了した外国人労働者と、雇用契約の締結を図ります。分野ごとに必要書類が異なるため注意しましょう。
つぎに、在留資格「特定技能1号」外国人支援計画の策定をします。支援責任者の氏名や役職などの詳細や登録支援機関の詳細、義務的支援(10項目)について記載します。
外国人支援計画完成後は、地方出入国在留管理局で在留資格変更許可の申請手続きをしましょう。無事に受理されれば、外国人労働者の就労が開始します。
在留資格「特定技能1号」の申請ではさまざまな書類作成をこなさなくてはならず、申請までに多くの手間や時間がかかります。不備が見られた場合は再提出を求められ、申請手続きに手間取ることが予想されます。
書類作成や申請手続きをスムーズに進めたい方は、行政書士の申請代行サービスをご活用ください。
【2025年最新】技能実習制度は廃止が予定されている

技能実習制度は廃止され、新たに「育成就労制度」が導入予定です。
現在の技能実習制度は、外国人が日本の技術を習得し、母国で活かすことを目的としています。しかし、実際は日本企業の労働力の確保が狙いとなるケースが多く、方向性が異なる点が問題視されています。
また、技能実習制度では転職が認められず、一度実習を開始したらほかの職種の実習が受けられません。そのため、実習先から失踪する技能実習生が多数発生しており、令和5年の技能実習生の失踪者数は9,753人と、近年で最も多い結果となっています。
育成就労制度では、外国人を実習生ではなく「労働者」として採用します。また、本人の意思で転職が可能となるため、外国人の労働環境が整えられる予定です。
育成就労制度は、2027年頃に施行が予定されています。
まとめ

在留資格「技能実習3号」は、在留資格「技能実習2号」で習得した技能などの熟達を目指す資格です。在留資格「技能実習3号」へ移行するには、試験の合格や一時帰国など定められた条件を満たす必要があります。
また、在留資格「技能実習3号」は在留資格「特定技能1号」への移行も可能です。移行時には、雇用企業側にさまざまな書類の提出が求められます。スムーズに申請手続きを進めるには、事前準備が重要なカギとなります。
申請に必要な書類の作成や窓口での申請手続きなど、時間や手間がかかる業務は行政書士の代行サービスを活用するのがおすすめです。申請経験豊富な行政書士が申請手続きを代わりに担い、外国人の採用業務をサポートいたします。
無料相談も承っているため、お気軽にご相談ください。