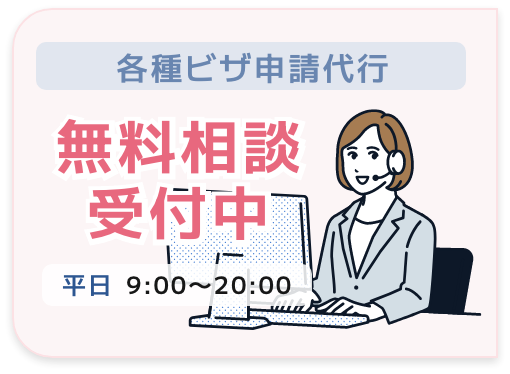これまで特定技能「介護」の外国人は訪問系サービスへの従事が長らく認められていませんでした。
しかし人材不足の状況などを踏まえ、2024年6月19日の有識者検討会で、特定技能外国人が訪問介護サービスに従事することを正式に容認する方針が決定され、2025年4月より制度として施行されています。
まだ施行されて間もないので、制度がよくわからない、とお困りの訪問介護事業所(ヘルパー事業所)の方も多いのではないでしょうか。
この記事では2025年4月に改正された内容について解説していきます。
訪問介護(ヘルパー)と特定技能の概要について
ここでは訪問介護(ヘルパー)と特定技能、それぞれの制度について説明していきます。まずはそれぞれの制度についてしっかりと抑えておきましょう。
訪問介護(ヘルパー)の基本情報
訪問介護(ヘルパー)とは介護保険制度に基づいて、介護職員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、身体介護(食事・排泄・入浴)や生活援助(掃除・洗濯・調理)を行うことです。
利用者の家族の家事やペットの世話などは生活援助には含まれません。
特定技能「介護」の制度とは?
特定技能「介護」とは、日本の介護分野の人手不足を改善するために作られた在留資格です。
日本では介護分野においてさまざまな人員確保の取り組みが実施されている反面、人材確保が困難な状況にあります。そのため、介護分野の専門性や技術を持ち合わせた外国人を積極的に受け入れる制度を設けました。
特定技能「介護」の人材は1人で夜勤が可能で、配属後すぐに人員配置基準に加われるなど、介護現場で即戦力となります。在留期限の上限がなくなる2号の制度はなく、1号のみ申請を受け付けています。詳しい内容は以下の記事で解説しています。
→特定技能「介護」とは?取得条件や注意点・企業側の必要要件などを解説
特定技能介護の訪問系への拡大!2025年の改正点について
訪問系サービスでは、ヘルパーと利用者が1対1で関わりながら介護サービスを提供します。
より専門的な介護の知識が必要とされ、利用者保護、緊急時対応への不安、監督体制の確保が困難であること等を理由に介護福祉士資格を取得した在留資格「介護」とEPA介護福祉士のみに認められる業務とされていました。
しかし、2024年6月19日の厚生労働省の発表にて、特定技能「介護」の訪問系サービスへの従事開始に関する情報が解禁されました。
特定技能による訪問介護(ヘルパー)解禁の背景
特定技能は2019年4月から始まった在留制度です。6年目を迎えた特定技能制度ですが、なぜいままで認められていなかった訪問介護が認められたのでしょうか。その背景について解説します。
訪問介護分野の深刻な人材不足
日本では少子高齢化に伴う労働人口の減少により、介護業界の人手不足は年々深刻化しています。
介護事業所への入職率が離職率を下回る状況が続いており、長期的な目線で見ても低下傾向にあります。
その中でも訪問介護は「通常業務に追われていて、教育・研修の時間が十分に取れない」、「訓練プログラムの機会が不足していて、スキルアップが難しい」などの理由により特に人手不足が深刻な分野です。
日本人職員の確保困難と外国人労働力の活用
介護職の賃金が低い理由に介護事業所に入る介護報酬では、従業員に十分な賃金を払えないという背景があります。
仕事の負担に対して給与水準が低いというマイナスのイメージが強くなっており、日本人職員の確保が難しくなっています。
そんな状況の中、特定技能外国人は介護職につくこと、スキルアップをして介護福祉士になることを目的に来日していますので、離職しないことへの期待は大きく、外国人労働者の役割は非常に重要なものになっています。
特定技能で訪問介護(ヘルパー)に従事するための条件
特定技能外国人が訪問介護(ヘルパー)に従事するためには、外国人側と訪問介護事業所側、それぞれに求められる要件があります。
特定技能外国人側が満たすべき要件
特定技能外国人に求める資格要件は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
| 日本語能力 | 日本語能力試験N3相当以上が望ましい |
| 介護スキル | 介護職員初任者研修を修了していること |
| 実務経験 | 原則1年以上の実務経験 (訪問系・施設系問わず) |
特定技能介護のビザを取得するための、介護の技能評価試験と日本語評価試験に合格していることが大前提となります。
訪問介護(ヘルパー)事業所側が満たすべき要件
訪問介護(ヘルパー)事業所側にもサービスの利用者と特定技能外国人、それぞれに対して果たすべき義務が定められています。
利用者側に対する義務
特定技能で訪問介護に従事する場合はサービスの利用者・家族へ「外国人介護職員が訪問する旨」の事前の説明が必要です。後々のトラブルを回避するためにも同意プロセスは明文化しておきましょう。
特定技能外国人に対する義務
特定技能外国人を雇用する上で義務づけられている支援に加え、訪問介護(ヘルパー)事業所側には特定技能外国人に対して以下のことを遵守する必要があります。
- 訪問系サービス業務の基本事項などに関する研修の実施
- 一定期間、責任者らが同行するなどの必要な訓練の実施
- 外国人へ業務内容などを丁寧に説明し、意向を確認
- キャリアアップ計画の作成
- ハラスメント対応のための相談窓口の設置
- 訪問先でのケア内容を見える化などのICT(情報通信技術)環境の整備
これらが適切に履行できる体制が整っていることの報告書作成と国際厚生事業団への提出も必要になりますので、制度利用を検討する際はしっかりと体制を整えておきましょう。
参考元:https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_56271.html
特定技能による訪問介護(ヘルパー)制度導入に寄せられる今後への期待
特定技能外国人が訪問介護を行えるようになったことで、介護業界はどのように変わっていくのでしょうか?今後の可能性について説明していきます。
長期的な外国人雇用による人手不足の解消
訪問介護は特に担い手が減少しており、地域によってはサービスが提供できない「空白地帯」が生まれています。外国人材の導入は、こうした問題を打破するための有効な手段とされています。日本人にとっては低賃金で重労働という感覚であっても、「本国に送金したい」、「日本に住みたい」という外国人からすれば価値のある・安定した仕事と捉えられることも多いです。特定技能外国人の採用にはコストもかかりますが、人が定着してくれるのであれば十分コストには見合います。
地域密着のグローバルで柔軟な対応が可能に
多様な文化的背景を持つ外国人ヘルパーが地域と連携することで、外国人家庭の文化や宗教に配慮した支援のほか、将来的には多言語対応の訪問介護も期待できます。
外国人材の教育は簡単ではありませんが、その先には、外国人による訪問介護サービスが地域に根付く社会の実現が見えてくるのではないでしょうか。
特定技能外国人による訪問介護(ヘルパー)の注意点と課題
今回の新制度には様々な期待も寄せられますが、同時に訪問介護(ヘルパー)事業所が留意しておくべき点もいくつかあります。
外国人ヘルパーの視点から見た訪問介護
訪問介護は「1対1の会話」が基本です。利用者の病状や生活背景を踏まえた柔軟な応答、日本的なあいまいな表現への理解が求められるため、形式的な語学力では不十分です。一人での訪問に不安を持つ特定技能外国人も多いのではないでしょうか。
訪問介護には語学だけでなく、日本の慣習や価値観も含めた包括的教育の実施が求められます。しっかりとした教育環境を整えることで、本人の自信にもつながり、責任感ややりがいを感じてもらえることになるでしょう。
外国人の労務管理と人権の保護
訪問系サービスでは利用者や利用者家族から外国人ヘルパーに対しハラスメント行為が発生した際に発見が難しいという課題があります。
ハラスメント防止策、万が一発生した場合の相談窓口の設置も検討する必要があります。
緊急時の対応など、訪問介護特有のリスク
外国人ヘルパーが訪問介護を行うに際に日本人職員とは異なるリスクがいくつか存在します。特に以下のようなリスクが顕著になることが考えられます。
- 容態の急変などの緊急時に適切な判断が遅れる
- 緊急時に医療機関への状況説明がうまくいかない
- 利用者の方言などが理解できず、行き違いの発生
- 食事サポートなどの際の文化的違和感
緊急対応マニュアルを外国人材向けに作成する、利用者家族への理解促進に取り組むことでこういったリスクを減らすことができます。
教育・支援体制確立の負担
受け入れ事業所にとって、外国人材育成のためのコストや体制整備は決して軽視できるものではありません。特定技能外国人の義務的支援を登録支援機関へ依頼する行政の支援策を活用するなど外部と連携して負担を減らしましょう。
訪問介護(ヘルパー)事業が特定技能の採用で取るべき今後の戦略
特定技能による訪問介護制度の理解
訪問介護事業者が特定技能制度を活用して訪問介護を行うには制度の概要・条件・義務についてまずはしっかりと理解をし、準備を進めることが重要です。厚労省・出入国在留管理庁のガイドラインには目を通しておきましょう。また特定技能の制度は頻繁に制度改正が行われていますので自分の認識が最新情報でない可能性もあります。注意しましょう。
支援体制の整備
制度の概要を理解したら、外国人材の受け入れに向けて準備をすすめましょう。
外国人向けの実務マニュアル作成や利用者向けの説明資料の準備もあると役立ちます。外国人の雇用は、単に人手不足を補う手段ではなく、地域や職場に多文化や多様性を受け入れていく大きなチャンスでもあります。そうした視点での職場づくりが今、求められています。自社ですべての支援が難しい場合は登録支援機関との連携を強化し、支援体制を構築しておきましょう。
地域住民との信頼関係構築
訪問介護において外国人材が地域に受け入れられるには、利用者や利用者家族の不安や違和感を軽減し、地域の仲間として迎えてもらう体制作りが大切です。
利用者向けのオリエンテーションを実施し、外国人ヘルパーがしっかりと日本語教育や介護研修を受けていること、コミュニケーションが問題なく可能であることを丁寧に説明しましょう。外国人ヘルパー訪問後も、実際に利用してどうだったか、フィードバックを収集するのもおすすめです。
人材確保加算などの制度活用
厚生労働省には人材確保等支援助成金など外国人労働者の就労環境整備を支援するための制度も用意されています。
外国人労働者に配慮した就労環境づくりを行うことで、一定の条件を満たせば助成金が支払われます。
こうした制度を活用することで、外国人材が安心して長く働いてもらえる環境づくりを進めるとともに、運営コストを抑えることも可能になります。
参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/gaikokujin.html
特定技能による訪問介護(ヘルパー)、結局のところどうなの?
2025年4月より解禁された特定技能による訪問介護サービスは結局のところ訪問介護事業にとって十分に活用できる制度となっているのでしょうか?それとも教育体制の整備やコストなど負担の方が大きいでのでしょうか?
制度活用の成功は「現場対応力」にかかっている
日本人ヘルパー希望者が減少している中、特定技能外国人を訪問介護に配置できるようになった意義はや期待は非常に大きいです。しかし訪問介護は、日本人でも難易度の高い分野です。外国人ヘルパーが安心して活躍できる環境整備には、言語・文化・教育・安全管理・対話力といった複合的な視点が求められます。準備と支援は不可欠ですが、制度自体の活用価値は高いものだと考えられます。そして外国人材の定着と経営の安定、両面を見据えた戦略的な環境整備が、これからの訪問介護事業に求められています。
専門家への相談も視野に
特定技能介護の資格で訪問介護を行うには様々な準備や支援体制の構築が必要です。MIRAI行政書士事務所では、こうした制度導入を検討されている訪問介護事業所様に対し、在留資格の取得支援だけでなく、制度運用に関する包括的なアドバイスを行っています。必要な書類作成から、登録支援機関との連携に至るまで、ぜひお気軽にご相談ください。