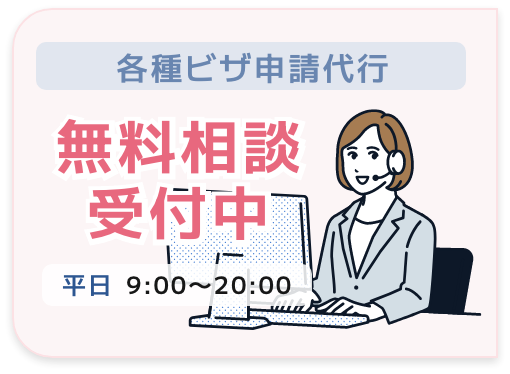「不許可通知が届いてしまった・・」
「再度申請をしたいがどうすれば許可を得られるのだろうか。」
在留資格申請の不許可通知を受けてしまうと、今後どのように動けばよいのか大変困ってしまいます。
今回は、申請が認められなかった場合に向けて、
- 不許可通知を受け取った後はどうすればよいか
- 再申請で挽回するための手順
- 再申請時に注意すべきポイント
これらについて、解説していきます。
不許可になってしまった場合でも、正しい方法で申請をすれば、再びチャンスを得ることができる可能性もあります。
不許可通知を受けた際の初動対応
では、不許可通知を受けた場合にはまずどのように行動をすれば良いのでしょうか。最初に必要であるのが、現在の状況を整理し、認識をすることです。
そして、今後の対策を立てるための準備を進めましょう。なぜなら、やみくもに再度申請を行ったとしても、同じ不許可通知を得ることになってしまう可能性が高いからです。
たとえば不許可となってしまった場合、入管局から不許可通知書という書面が届きます。却下となってしまった理由が明記されている場合も多いため、これを読み解くことが改善の第一歩となります。こうしたポイントを確認し、適切な初動を取ることが再申請での成功につながりますので、さらに以下にて解説いたします。
不許可理由を入管局で確認する
まず、不許可通知を受けた場合には、可能な限り、入管局でその不許可となってしまった理由を直接確認してみましょう。不許可の理由は人によってそれぞれ異なっており、通知書に記載されている内容でからは、詳細が分からないこともあるからです。その点、入管局で理由を確認できれば、今回の申請についての詳細を把握できます。
入管局では窓口で相談できる時間が決まっているため、事前に電話で予約や確認を行いましょう。 参考:「外国人在留総合インフォメーションセンター等」出入国在留管理庁
担当者から具体的な不許可理由を聞きくことができれば、再申請の際に改善すべき点も明確になります。不許可になってしまう理由は様々であり、書類の不備、不足から、申請要件の不足、犯罪歴や違反歴といったものが挙げられます。入管局で理由を告げられたが、さらに理解できない点があった場合には、行政書士などの専門家へ相談をしてみましょう。不許可理由について、いっしょに考えてもらえます。
不許可通知書の内容を詳細に把握
そして、不許可となってしまった場合、その理由を確認する次の方法として、不許可通知書の内容を確認することが重要です。不許可となってしまった場合には、不許可通知書という書面が郵送で届きますが、そこに不許可の理由が記されているため、まずはその内容を確認しましょう。
不許可通知書には例えば以下のような内容が書かれています。
・必要な書類が不足している
・収入基準を満たしていない
通知書を読んでみても、それでもどの点が不許可につながってしまったの分からないといった場合には、通知書を持参して、入管局の窓口でさらに問い合わせをしてみましょう。そして、通知書に記載されている内容意味が分からない、文言がわかりにくいといった場合には、入管の窓口のほか、行政書士などの専門家に相談をするのもひとつの方法です。
不許可の主な理由と対策
不許可通知を受けた後、再申請で許可を得るためには、不許可となった主な理由を正確に把握し、それぞれに応じた具体的な対策を講じることが重要となります。不許可とされてしまう理由には、申請要件の未達、書類の不備、犯罪歴や違反歴、収入・扶養家族の基準未達、転職や在留期間の短さ、年金・保険未加入、理由書や身元保証人の不備など、さまざまなものが考えられます。それぞれの理由について、対処方法がことなるため、再申請で成功を目指す方は、まずどの理由に該当するかを明確にしましょう。参考:「就労ビザの申請の不許可事例とは?更新時に見られるポイント解説」
申請要件を満たしていない場合
申請の際にもっとも重要な点、これは申請要件を満たしていることです。よって、申請要件を満たしていない場合には、不許可となってしまうことは当然の結果であると言えます。
申請要件を満たしていない例としては、在留資格の基準に見合っていないこと、法律で定められた条件に合致していないこと、などが挙げられます。さらに詳しくお伝えすると以下のような例があります。
・在留資格ごとに必要とされる学歴や職歴を満たしていない。
・収入要件を満たしていない。
・在籍企業の規模が十分でない。
・家族構成の要件が十分でない。
入管は書類上で厳密に判断しますので、まずは申請要件をしっかりと確認し、どの要件が足りていないのかを明確にしましょう。足りていない要件がわかったら、説明をするための追加資料を準備し、申請内容が基準に沿っていることを説明できるようにしましょう。申請要件を満たしていない場合、書類を補うことやていねいな説明に変えること、などの工夫で挽回できる可能性もあります。
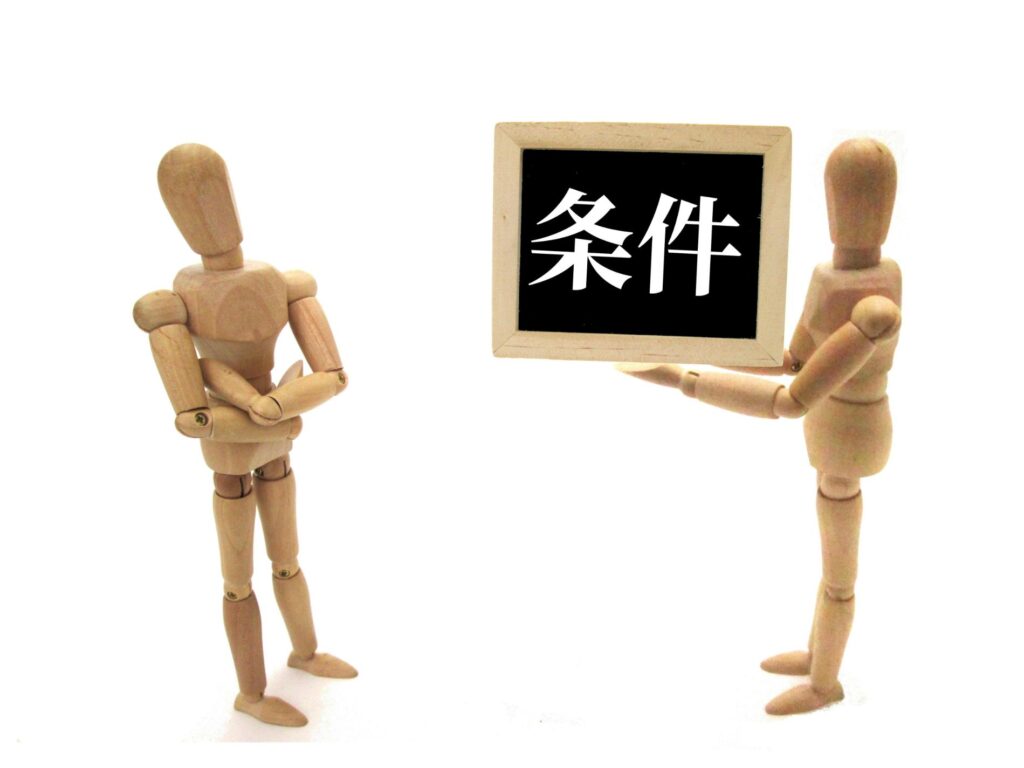
書類不備を防ぐための注意点
書類の不備があった場合、これも不許可を避けられません。そのため、申請をする際には、提出前に不備、不足がないかどうか、十分に確認をしておくことが重要です。
書類の不備として挙げられる具体的として、以下のようなものが考えられます。
・記載漏れ。
・必要書類の添付忘れ
・証明書の期限切れ
申請書類に不備があると、審査が止まってしまったり不許可となる可能性が高まります。ご自身で手続きを行う際には、漏れのないよう、申請書のチェックリストを作成して準備をするのもおすすめです。
また、必要となる書類は、随時変更となる可能性もあるので、入管局のウェブページなどで最新の情報もチェックするようにしましょう。ご自身での確認が難しいと感じられる場合には、より安心できる方法として、提出前に行政書士などの専門家に相談をし、確認してもらう方法も大変有効です。
犯罪歴や違反歴の影響を理解する
犯罪歴や入管法違反歴が見られた場合、これも不許可通知の大きな理由として挙げられます。過去に刑事事件で有罪判決を受けたり、在留資格のルールを破った経歴、大きな交通事故を起こした経験があると、審査で不利になることが多いです。そのような犯罪歴や違反歴があった場合、入管局は再度問題が起こってしまう可能性を考えて慎重に判断するためです。
ただし、違反をしたからといって、不許可となる可能性が避けられないわけではありません。違反をしたその内容や、違反からの年数、反省の態度などが考慮されることもあります。犯罪歴や違反歴により不許可となってしまった後の再申請時には、違反の経緯や現在の状況、反省していることを説明する書面を用意し、誠実な態度を示しましょう。そして犯罪歴や違反歴がある方は、行政書士などの専門家のアドバイスを受けることで、より適切な対応策を見つけることができるかもしれません。
収入や扶養家族に関する基準
収入や扶養家族に関する基準を満たしていないと、不許可通知を受ける原因となり得ます。在留資格の「経済的に安定した生活が送ることができるか」という点を重視しているためです。
具体的には、申請者本人の年収が一定額を下回っていたり、扶養家族が多すぎて生活が難しいのではないかと判断された場合には、認められにくい傾向があります。要件として問題がないのであれば、経済的に安定した生活を送ることができることを示すための、過去1年分の給与明細や源泉徴収票を用意し、証明することが大切です。家族構成に対する具体的な生活費の内訳を示して、安定した生活を送ることができる旨を説明することも有効であるといえます。このように、安定した生活基盤を証明することが再申請の鍵となるでしょう。
転職や在留期間が短い場合の対策
転職直後や在留期間が短い場合も、不許可通知を受ける可能性があります。これは、安定した生活基盤や就労状況が証明されにくいことが理由です。再申請で成功をするためには、新しい勤務先での雇用契約書や給与明細、在職証明書を提出し、現在の就労状況を具体的に説明できるようにしましょう。
転職をした理由、これからの生活設計を理由書の中で、誠実な姿勢をもって詳しく説明するのも良いでしょう。在留期間が短く不許可となってしまった場合は、これまでの日本での生活実績や納税・年金・保険の記録をしっかり提出し、問題のない生活を送れていることを示すことが大切です。
年金・保険の加入状況を確認
年金や健康保険への加入状況に不備や不足があること、これも在留資格の申請や更新で不許可通知を受ける要因となります。日本で生活をする上では、これらの社会保険制度は最低限の義務とされているためです。
それでは、うっかり保険料の支払いを忘れていた場合はどうすればよいのでしょうか。まずは市区町村役場や年金事務所で、現在の加入状況、納付状況を確認し、未納分については速やかに納付をしましょう。そして支払い済であることの証明書を取得し、再申請をするようにしてください。
理由書や身元保証人の重要性
理由書は、不許可の通知を受けた後、再申請をする際には大変重要な書類となります。理由書にて、書類に不足がある部分を挽回できる可能性があるからです。なぜ前回の申請が認められなかったのか、その理由をしっかりと把握し、再申請の際には理由書で反省点や改善策を具体的に説明しましょう。理由書で現在の申請者の立場や状況を伝えることで、審査官の理解を得やすくなります。
そして、身元保証人の存在も重要です。申請者の日本での生活を支える存在として、審査の際の信頼性を高ると言えるでしょう。特に家族や勤務先の責任者が保証人になると、審査の印象が良くなる傾向があります。どのような人を身元保証人とすればよいかについて悩む場合には、行政書士などの専門家に相談をしてみましょう。
再申請で許可を得るためのステップ
再申請の可能性を専門家に相談
再申請を検討する際の方法について説明をしてきましたが、もっとも安心できる方法は、まず専門家に相談することです。入管からの不許可通知は一人ひとり理由が異なり、申請者の自己判断が難しく、また再申請でも不許可となってしまう可能性があるからです。
専門家は過去の事例であったり、最新の法律の改正、制度の変更にも精通しており、あなたの状況に合わせた具体的なアドバイスを提供できるといえるでしょう。行政書士や弁護士などの専門家に相談すると、不許可理由について詳しく調べることができますし、必要な追加書類についてもより確実に揃えることができます。そして、説得力ある理由書の作成方法についてもアドバイスを受けることができるでしょう。結果として、専門家への相談により再申請の際の成功率高まると思われます。
不許可通知や再申請に関するよくある質問
次に、不許可通知を受けた際、もしくは再申請を検討する際の対応方法として、よく見られる質問について解説します。
不許可通知を受けた後の流れ
上記でも述べましたが、不許可通知を受けた後には、まず不許可となった理由を確認することが重要です。まずは、不許可通知書の内容をしっかりと確認しましょう。慌てて、準備が不十分なまま再度申請をしても不許可につながってしまう可能性もあるため、不許可となった原因の洗い出しが必要です。
そして、今後どのような手続きをとるべきなのかについて把握しましょう。どのような書類が必要なのか、理由書の準備など、今後の手続きの流れを確認した上ですすめましょう。また、専門家への相談も視野に入れることがおすすめです。
再申請時に必要な書類とは
再申請時には、最初の申請時よりも慎重に必要書類を準備しましょう。再申請で求められる主な書類は、申請書、写真、パスポート、在留カード、不許可通知書の写し、理由書、追加資料などになります。
特に理由書では、前回不許可となってしまった理由を踏まえて、どのように改善したかを具体的に説明するしましょう。前回の不許可理由をきちんと把握し、それに沿った追加資料や説明を添えることが、許可を得るための近道です。また、収入証明や年金・保険の納付状況、身元保証人の書類など、指摘された点に不足がないことを説明するための資料も準備しましょう。
まとめ:不許可通知を受けた際の再申請で挽回する方法
今回は、不許可通知を受けた場合の、
- 不許可通知を受けた際にまず取るべき対応
- 不許可理由の確認と改善ポイントの見極め方
- 再申請時に注意すべき具体的な手順
上記について、解説いたしました。