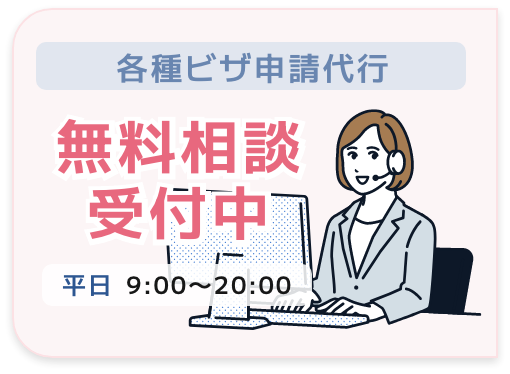2024年3月29日より、在留資格「特定技能」に鉄道分野の追加が発表されました。鉄道分野の人材不足の解消を目的とし、一定の知識や技能を持つ外国人労働者の積極的な雇用が進められています。
在留資格「特定技能」の鉄道分野で外国人を雇用するには、申請者本人はもちろん雇用企業側も定められた条件を満たさなくてはいけません。
今回は、在留資格「特定技能」の鉄道分野について詳しく解説します。主な業務区分や業務内容、雇用企業が満たすべき条件などを知りたい方は、参考にしてください。
また、在留資格保有者の採用には、MIRAI行政書士事務所の申請代行サービスをご活用ください。書類作成から窓口申請、受け取りなどさまざまな業務を代行し、サポートいたします。
【最新】在留資格「特定技能」に鉄道分野が追加

2024年3月29日に特定技能制度で新たに追加が決定したのは、以下の4分野です。
- 自動車運送業
- 鉄道
- 林業
- 木材産業
上記の分野は、2024年9月30日より受け入れが開始されています。
参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/2024.03.29.kakugikettei.html
鉄道分野追加の理由は「将来の人手不足解消」
鉄道業界では人手不足が続いており、職員数は年々減少しています。
1989年に約27万人いた鉄道職員は、2021年に約19万人まで減少しました。鉄道職員の減少は保線作業や運転士の不足を招き、列車の減便や終電時間の繰り上げなど、鉄道業界にさまざまな影響が出ています。
なお、令和10年には約1万8,400人もの人材が不足すると予想されています。
対して鉄道の利用者数は、コロナショック前の約9割程度まで徐々に回復しているのが現状です。鉄道分野では、利用者数が戻りつつある現状に対応するための人材確保が課題といえるでしょう。
在留資格「特定技能」の鉄道分野では、今後5年間で最大3,800人の受け入れが想定されています。鉄道分野の追加は、将来の人材確保に向けた重要な一歩となるでしょう。
参考:https://www.moj.go.jp/isa/content/001416436.pdf
在留資格「特定技能」の鉄道分野の特徴

在留資格「特定技能」の鉄道分野では、従事可能な業務が定められています。ここでは、在留資格「特定技能」の鉄道分野の特徴を紹介します。
- 業務区分は全部で5つ
- 鉄道業は在留資格「特定技能2号」の対象外
業務区分は全部で5つ
主な業務区分と業務内容は、以下の表のとおりです。
| 業務区分 | 業務内容 |
| 軌道整備 (軌道等の新設、改良、修繕に関する作業・検査業務など) | ・軌道検測作業 ・レール交換作業 ・まくらぎ交換作業 ・バラストを取り扱う作業 ・保安設備を取り扱う作業 |
| 電気設備整備 (電路設備、変電所の設備、電気機器等設備、修繕に関する作業・検査業務など) | ・電路設備 ・変電所設備 ・電気機器設備 ・信号保安設備 ・保安通信設備 ・踏切保安設備 |
| 車両整備 (鉄道車両の整備業務) | ・装置、連結装置等や車両部品の検査、修繕・構内入換 ・駅派出対応 ・改造工事 ・定期や臨時の清掃業務 ・在庫や予備品の管理 ・工場設備取扱い |
| 車両製造 (鉄道車両、鉄道車両部品等の製造業務など) | ・素材加工 ・部品組立て作業 ・構体組立て ・塗装 ・溶接 ・艤装 ・台車枠製造 ・台車組立て ・電子機器組立て ・電気機器組立て ・試験や検査 ・部品検収や配線業務 |
| 運輸係員 (駅係員、車掌、運転士など) | ・ポイント操作 ・入換え合図 ・駅設備管理や取扱い業務 ・旅客案内や貨物の取扱い業務 ・運行管理業務 ・車掌業務 ・運転士業務 |
上記5つの区分においては、作業場所の整理や清掃、業務に関する事務作業などへの従事も可能な範囲とします。
参考:https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/10_00179.html
鉄道業は在留資格「特定技能2号」の対象外
在留資格「特定技能」は、1号と2号の2つの在留資格が設けられています。鉄道分野は在留資格「特定技能2号」の対象外分野のため、在留資格「特定技能1号」のみ取得可能です。
在留資格「特定技能1号」の在留期間は最長5年までとなり、家族の帯同は認められません。鉄道分野では、在留資格「特定技能2号」の受け入れ制度は数年後に新設される可能性はありますが、現時点で存在しないため注意しましょう。
在留資格「特定技能1号」と「特定技能2号」の違いについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
特定技能ビザとは?あてはまる業種や取得条件、取得の流れを詳しく解説
在留資格「特定技能」の鉄道分野に従事するための条件

在留資格「特定技能」の鉄道分野に従事するには、定められた条件を満たす必要があります。在留資格「特定技能」の鉄道分野に従事するための条件は、主に以下のとおりです。
- 鉄道分野特定技能1号評価試験の受験
- 日本語試験の合格
鉄道分野特定技能1号評価試験の受験
在留資格「特定技能」の鉄道分野に従事するためには「鉄道分野特定技能1号評価試験」を受験しなくてはいけません。
鉄道分野特定技能1号評価試験は、電気設備整備や軌道整備など携わる業務によって試験内容が異なります。携わりたい分野の試験を選びましょう。
鉄道分野特定技能1号評価試験は学科試験と実技試験があり、日本語で実施されます。「鉄道分野特定技能1号評価試験(軌道整備)」のみ、技能検定3級の受験も必要です。
日本語試験の合格
鉄道分野特定技能1号評価試験だけでなく、日本語能力に関する試験の合格も必須条件となります。
日本語試験に関する主な受験内容は、以下の表のとおりです。
| 業務区分 | 日本語能力 |
| 運輸係員 | 日本語能力試験(N3以上) |
| 運輸係員以外(軌道整備、電気設備整備、車両整備、車両製造) | 日本語能力試験(N4以上)または国際交流基金日本語基礎テスト |
運輸係員の業務へ従事する場合は、業務上会話の頻度が多いことなどから日常的な日本語をある程度理解できる「N3以上(中級レベル)」が求められます。
在留資格「技能実習2号」から移行する際は試験が免除される
在留資格「技能実習2号」を修了している場合、鉄道分野特定技能1号評価試験と日本語能力試験の免除対象とみなされます。
ただし、免除には以下の条件を満たさなくてはいけません。
- 技能実習2号を良好に修了している
- 技能実習制度の職種や作業内容が移行対象分野と関連性がある
なお、運輸係員は移行が認められていないため注意しましょう。
在留資格「特定技能」の鉄道分野の雇用で企業が満たすべき要件

在留資格「特定技能」の鉄道分野で外国人を雇用する際は、外国人労働者とは別に雇用企業側でもさまざまな準備を進める必要があります。また、採用後も継続的なサポートをしなくてはいけません。
在留資格「特定技能」の鉄道分野の雇用で企業が満たすべき要件は、主に以下のとおりです。
- 鉄道分野特定技能協議会への入会
- 国土交通省の調査への協力
- 適切な就労管理
鉄道分野特定技能協議会への入会
在留資格「特定技能」の鉄道分野で外国人材を雇用する際は、雇用前の「鉄道分野特定技能協議会」への入会が必須です。
鉄道分野特定技能協議会は、外国人材の適正な受け入れと権利の保護を目的としています。特定技能協議会への事前加盟制度は、2024年6月15日以降の在留資格の申請から義務化されました。
在留資格「特定技能」の鉄道分野で外国人材を雇用する際に鉄道分野特定技能協議会への入会を怠ると、在留資格「特定技能」に該当する外国人の受け入れができません。外国人の在留申請前に、必ず鉄道分野特定技能協議会への入会手続きを済ませておきましょう。
国土交通省の調査への協力
雇用企業は、鉄道分野特定技能協議会だけでなく国土交通省への協力も必須条件です。
在留資格「特定技能」の鉄道分野で外国人を採用した場合、国土交通省や国土交通省の委託先から、雇用に関する調査依頼が入る場合があります。調査の協力を求められた際は、誠実に対応していきましょう。
適切な就労管理
在留資格「特定技能」の鉄道分野で労働する外国人を雇う際は、出入国在留管理庁へ事前の申請はもちろん、就労後の管理状況の共有も求められます。
就労後の必要な届け出には、定期届け出と随時届け出があります。
| 届け出の頻度 | 届け出の期日 |
| 随時 | 外国人の就労開始から14日以内 |
| 定期 | 対象年の4月1日から翌年3月31日までのものを翌年4月1日から5月31日までに提出 |
定期届け出の頻度は令和7年4月1日より、四半期ごとから1年に1回へ変更されました。定期届け出には、特定技能外国人の労働日数や労働時間数、給与の支給総額などを記載します。
就労管理に必要な届け出は、管轄の地方出入国在留管理官署に持参または郵送、電子届け出システムから提出をしましょう。
在留資格「特定技能」の鉄道分野で外国人を雇用する際は、申請手続きに必要な書類の作成や申請窓口への訪問など、手続きが完了するまでにさまざまな手順を踏む必要があります。時間や手間のかかる申請手続きは、行政書士の申請代行サービスをご活用ください。
まとめ

人材不足が深刻な鉄道業界では、2024年9月30日より特定技能ビザの受け入れが開始されました。一定の知識や技能を持つ外国人労働者の積極的な雇用は、将来の人手不足を解消するための大きな一歩といえるでしょう。
在留資格「特定技能」の鉄道分野で外国人を雇用するには、申請者本人はもちろん雇用企業側も定められた条件を満たさなくてはいけません。雇用前の鉄道分野特定技能協議会への入会や雇用後の適切な就労管理が求められるため、手続きや書類作成に必要な情報は早めに整理しましょう。
申請手続きは、手間や時間がかかり、不備がみられた場合は再度申請を求められます。手続きをスムーズに進めたい方は、行政書士の申請代行サービスを活用してみてはいかがでしょうか。
無料相談も承っているため、お気軽にご連絡ください。