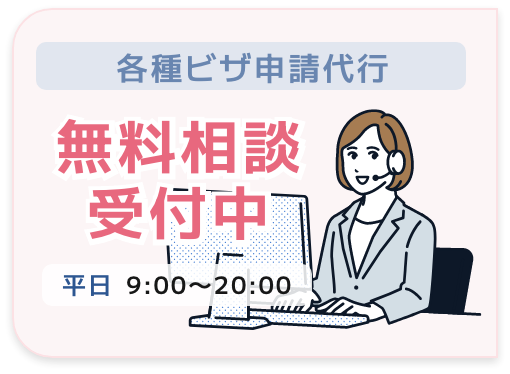外国人労働者が日本で働くためには、外務省が発行している在留資格を取得しなければなりません。しかし、日本で働くことを目的とした就労ビザは、複数種類あるうえ、それぞれ有効期間も異なります。本記事では、安心して外国人を雇うために把握しておきたい、就労ビザの有効期間や更新手続きの方法などを解説します。長く雇うために必要な就労ビザに関するポイントを網羅しているので、外国人労働者を雇いたい、もしくは雇っている企業の方はぜひ参考にしてみてください。
就労ビザの申請は豊富な実績を持つMIRAI行政書士事務所にお任せください。無料相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
就労ビザの種類と有効期間

2025年2月時点で、外務省から発行されている、長期滞在可能な就労ビザの種類は以下のとおりです。
| 就労ビザ | 有効期間 |
| 高度専門職1号イ、ロ及びハ | 5年 |
| 教授 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 芸術 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 宗教 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 報道 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 経営・管理 | 5年、3年、1年、6月、4月又は3月 |
| 法律・会計業務 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 医療 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 研究 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 教育 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 介護 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 企業内転勤 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 興行 | 3年、1年、6月、3月又は30日 |
| 技能 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 特定技能 | 1号:1年、6月又は4月2号:3年、1年又は6月 |
| 技能実習 | 技能実習1号イ及びロ:法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) 技能実習2号イ及びロ:法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) 技能実習3号イ及びロ:法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) |
| 外交 | 外交活動を行う期間 |
| 公用 | 5年,3年,1年,3月,30日又は15日 |
参考:https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/chouki/index.html
取得する就労ビザの種類によって、有効期間も大きく異なります。ここでは、一般的な企業で働くために取得するケースが多い、以下の在留資格をピックアップして、有効期間や職種に関する情報をより深掘りして解説します。
- 技術・人文知識・国際業務
- 特定技能
- 技能実習
誤った申請をしてしまい、後々大きな問題に発覚しないためにも、これから外国人労働者を雇おうと考えている方は、ぜひ念入りにチェックしてみてはいかがでしょうか。就労ビザの基本的な情報について知りたい方は、以下の記事に基礎知識をまとめているので、参照してみることをおすすめします。
就労ビザとは?外国人を雇うなら知っておきたい重要手続きを徹底解説
技術・人文知識・国際業務
技術・人文知識・国際業務は5年、3年、1年又は3月の在留期間を得られる在留資格です。機械工学等の技術者や通訳、マーケティング業務従事者など、日本にある企業で会社員として働く場合は、技術・人文知識・国際業務の就労ビザを取得することになります。技術・人文知識・国際業務のビザでの雇用形態は、一般的な正社員としての雇用の他にも、委任や嘱託、アルバイトなどの形態も含むことが可能です。しかし、実際に働いている仕事内容が、在留資格審査で認められた仕事の内容と一致している必要があるので、アルバイトで異なる仕事を始める際には資格外活動許可が必要です。
特定技能
特定技能は、人手不足が深刻な産業分野を対象にした在留資格です。
特定技能1号と特定技能2号に分かれており、在留期間や違いは以下のとおりです。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
| 資格概要 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
| 在留期間 | 通算で上限5年まで | 更新の上限なし |
| 技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号修了者は試験等免除) | 試験等で確認 |
| 日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号修了者は試験等免除) | 試験等での確認は不要 |
| 家族の帯同 | 基本的に認めない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
特定産業分野として認められている職種は、以下のとおりです。
- 介護
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 宿泊
- 自動車運送業
- 鉄道
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 林業
- 木材産業
技能実習
技能実習は開発途上国の人材を受け入れ、技術やノウハウの獲得を目的として設けられた在留資格 です。技能実習1号、2号、3号に種類が分けられており、それぞれの概要は以下のとおりです。
- 技能実習1号:最長在留期間は1年、技能を習得する活動とともに指定された講座を受ける
- 技能実習2号:最長在留期間は2年、技能検定等の試験に合格した後に実践的な技能を習得する
- 技能実習3号:最長在留期間は2年、実践的な技能に熟達する
最初に技能実習1号で技術を学び、技能検定などの試験に合格することで、技能実習2号の資格を獲得できます。技能実習1号から技能実習2号に移行できる職種は、農業関係など60種類以上に及びます。
さらに技能実習2号を経て、在留資格を技能実習3号に更新することが可能です。技能実習3号を取得すれば、さらに2年間の日本滞在が許可されます。
在留期間の決まり方

日本における行動や企業の働き方によって、同じ就労ビザを取得していても、更新期間が異なるケースは珍しくありません。そのため、在留期間が決まる仕組みを理解していないと、せっかく取得したのに早々に在留期間が切れてしまう事態に陥る可能性が高くなります。ここでは、在留期間を延長させるためにも知っておきたい、在留期間の決まり方に関する情報を解説します。
初回の在留期間は1年のことが多い
初めて就労ビザを申請した場合、問題行動を起こしていない外国人であっても、在留期間を1年に設定される可能性が高いです。初めて就労ビザを獲得した際には、更新サイクルが他の人よりも短いケースが多いので注意しましょう。在留期間中にあまり活動実績がない人の場合は、更新しても初回に申請した場合と同様に、在留期間を1年に設定される傾向があります。
在留期間中の素行により決まることも
在留期間中に税金の未納や滞納、在留資格に関する届出義務に応じていないと、法務省から「要観察」とみなされてしまいます。「要観察」になってしまうと、在留期間が短くなってしまうだけでなく、場合によっては在留資格を取り消される事態にまで発展します。また、在留期間中に犯罪を起こしてしまうと、強制送還の処置をとられることもあります。
就労ビザ更新で在留期間を延ばそう
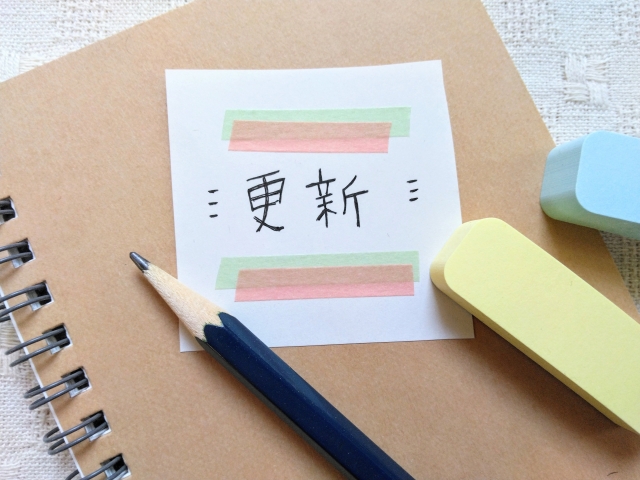
外国人労働者を引き続き雇用したい場合は、就労ビザの更新が必要です。仕事内容に変化がない場合は、「単純更新」という比較的スムーズな申請方法で更新作業に対応できるので、余裕を持ったスケジュールで行動すれば、とくに難しい対処をすることはないでしょう。有効期間まで3か月〜6か月以上の余裕がある場合は、「就労資格証明書」を取得すると良いでしょう。追加費用が発生するデメリットはありますが、よりスムーズに単純更新申請を進められるため、更新作業で手間取りたくない方におすすめです。
転職や社内の移動があり、仕事内容が変わってしまう場合は、変更する予定の仕事内容に適した就労ビザを取得する必要があります。在留期間の更新作業とビザの変更申請を同時並行で対応する必要があるので、余裕を持たせたスケジュールを心がけましょう。
就労ビザ申請のステップと必要書類の準備方法

就労ビザを申請するにはさまざまな書類や手順をクリアしなければなりません。ここでは「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザ(技人国ビザ)を例にとり、申請に必要な書類と申請方法を解説します。
技人国ビザを申請するには、以下の書類が必要です。
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
- 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記のうえ,404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
- 日本での活動内容に応じた資料
技人国ビザは、企業の規模によって4つのカテゴリーに分かれ、必要な書類が異なるので、自社はどのカテゴリーに該当するか事前に確認しておきましょう。必要な書類をそろえたら、以下の手順で申請手続きをクリアします。
- 入国管理局に在留資格認定証明書交付を申請する
- 在留資格認定証明書交付を受け取る
- 在留資格認定証明書を外国人労働者本人に送付する
- 外国人労働者本人が在留資格認定証明書を在外日本公館で提示し、ビザを申請する
- 在外日本公館にてビザ発給する
手続きを完了する期間の目安は申請書の提出から1〜3か月です。
就労ビザの更新ができない事例

申請内容と実際の働き方が乖離していると、就労ビザが更新できない可能性があります。ここでは、就労ビザの更新ができない事例を2つ解説します。就労ビザの更新ができないと、人材が足りないといったトラブルに発展する可能性があるので、安定した経営基盤を作るためにも、しっかりと把握しておきましょう。
学業と就業内容が一致していなかった事例
日本の専門学科や大学に通っていた場合、日本で学んだ知識やスキルと違う分野の職務で更新しようとすると、関連性が認められず、就労ビザの更新ができない場合も珍しくありません。たとえば、農業系の専門学科を卒業したものの、アパレル業界で働こうとすると関連性がないことから、ビザの更新を認められない恐れがあります。
在留状況が悪かった事例
税金を納付していない、指定された書類を提出していないなど、在留状況が悪い場合は、ビザの更新を認められない可能性が高いです。また、犯罪を犯してしまうと更新が認められないだけでなく、強制送還されてしまうこともあるので、在留中の立ち振る舞いには注意が必要です。
まとめ

就労ビザの種類は多種多様であり、外国人労働者がどのような職種で働くかによって、必要な書類や在留期間が異なります。また、就労ビザの有効期間を維持するには、在留中の模範的な生活態度が大切です。就労ビザを活用して長く働くためにも、申請・更新手順の対応を適切にするだけでなく、外国人労働者の在留中の立ち振る舞いにも気を配るように心がけてみると良いでしょう。
就労ビザの期間や更新手続きに関するお悩みはMIRAI行政書士事務所にご相談ください。